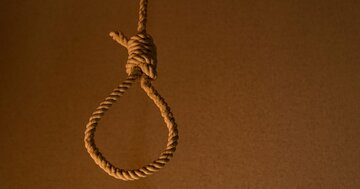もちろん、その年ごとの無期刑受刑者を見ている数字ですので、無期刑受刑者の全員が長期間入っているわけではありません。法務省の在所期間に関するデータによれば、2022年末の段階で、10年未満の者が無期刑受刑者全体の12.6%、10年から20年の者が46%、20年から30年の者が23.7%、30年から40年の者が13.2%、40年から50年の者が3.9%、そして50年以上の者が0.6%いるとされています。
年齢構成としては、20歳代の1.3%が最も少ない年齢層で、50歳代の24.1%が最大となり、次いで70歳代22.6%となっています。80歳代以上も7.8%おり、法務省の公表しているデータでは最高齢が何歳なのか判明しませんが、仮釈放審理状況を示すデータでは、許可されなかった受刑者の判断時の年齢が「90歳代」と記されている人がいることから、少なくとも1人以上は90歳以上の人も収容されていることが分かっています。
検察庁からの新ルール通達で
仮釈放のハードルがさらに高く
さらに、すでに終身刑としての運用がなされていると言えるような実態が少しずつ明るみになってきています。それは「マル特無期」の存在です。
1998年6月18日に最高検察庁は「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について(依命通達)」(最高検検第887号)いわゆる「マル特無期通達」を各地の検事長や検事正に向けて発出しています。通達による運用であるため、法律として議論されたわけではなく、この存在自体はしばらく知らされていませんでした。そのマル特無期通達の存在は2002年1月8日の朝日新聞の夕刊で報道されて初めて世間が知ることとなっています。
報道によれば、マル特無期通達の中身は「動機・結果の悪質性のほか前科や前歴などから同様の重大事件を再び起こす可能性が特に高いなどと判断した事件について地検や高検は最高検と協議し、指定事件に決まると判決確定直後に刑事施設側に「安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時は特に慎重に検討してほしい」と文書で伝え、関連資料を保管すること。