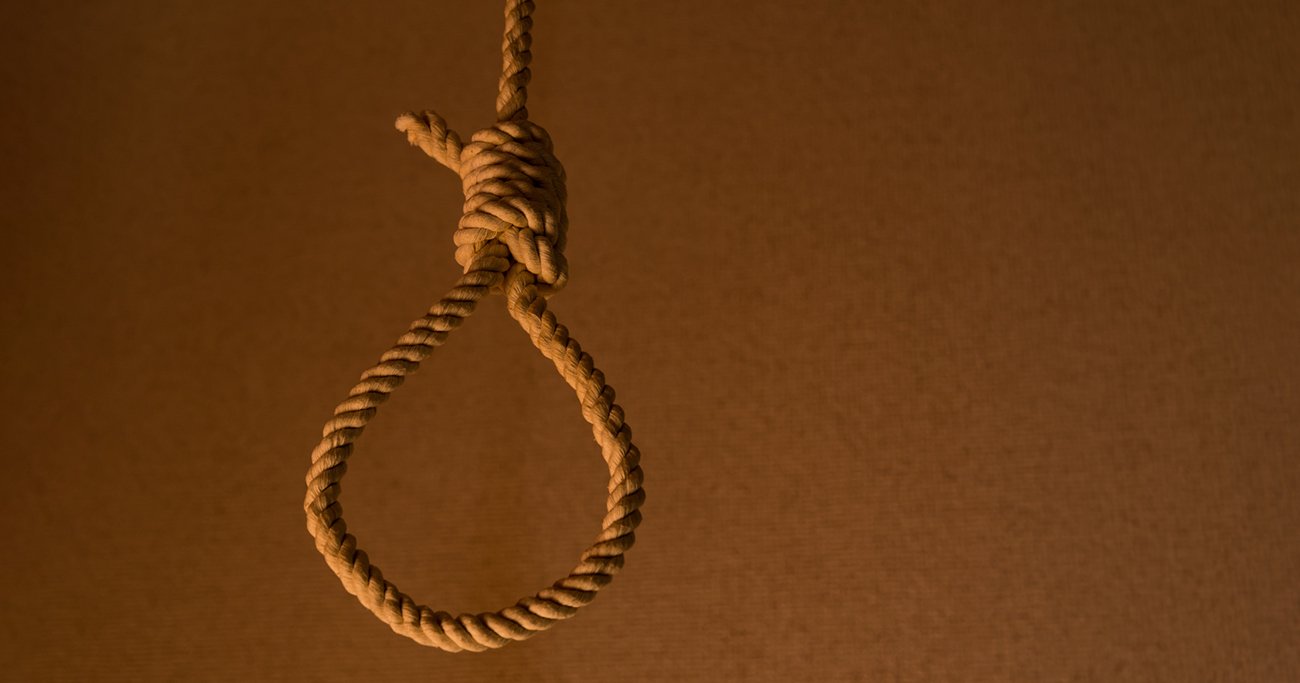 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本の死刑制度は、戦後からほとんど見直されることなく続いてきた。その背景には、「絞首刑は残虐ではないから、憲法違反ではない」という前提を支える、ある医学的鑑定の存在がある。70年以上にわたって信じられ続けてきた死刑の“常識”に迫る。※本稿は、丸山泰弘『死刑について私たちが知っておくべきこと』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。
「絞首刑は残虐ではない」は
どのような根拠がある?
絞首刑による執行によって被執行者が死に至る経緯が日本の刑事裁判で医学的証拠によって示されたのは、1952年10月に東京高等裁判所で行われていた控訴事件においてでした。その証拠とされるものが同年10月27日付で提出された東京大学医学部教授で法医学の権威であった古畑種基博士による鑑定書でした(以下、古畑鑑定とします)。古畑博士は、法医学の観点からどのように絞首刑によって死に至るのかを同裁判で次のように説明しています。
頸部に索条をかけて、体重をもって懸垂すると(縊死し)、その体重が20キログラム以上あるときは左右頸動脈と両椎骨動脈を完全に圧塞することができ体重が頸部に作用した瞬間に人事不省に陥り全く意識を失う。それ故定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるということは、法医学上の常識になっているのである。
(中略)
絞殺が最も理想的に行われるならば、屍体に損傷を生ぜしめず、且つ死刑囚に苦痛を与えることがなく(精神的苦痛は除く)且つ死後残虐感を残さない点に於て他の方法に優っているものと思う。







