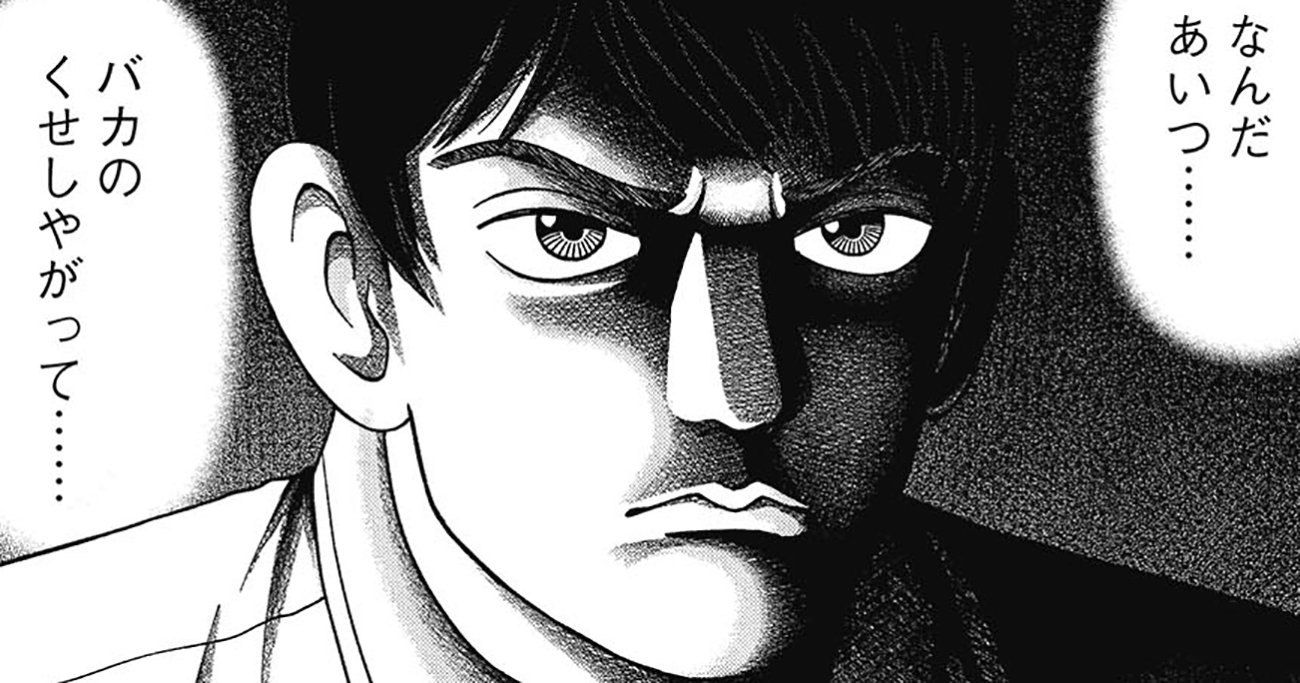 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第80回は、学習塾各社が開く「東大模試」について考える。
東大受験生には「あまり意味がない模試」もある
初めての東大模試に挑む天野晃一郎は、同級生の藤井遼に自信があるかと尋ねられたが、「ボクに自信あってもなくても藤井くんにはどうでもいい」と言い返す。恥をかいた藤井は「なんだあいつ……バカのくせしやがって」と悔しがるのだった。
一口に模試といっても、いろいろな種類がある。幅広い層を対象とする記述型の全国模試や、共通テスト形式の模試、各大学の入試形式に合わせた「冠模試」など、さまざまだ。
すべての模試を合わせれば、2週間に1回くらいはどこかの塾でやっているような状況だから、どの模試を受けるかは慎重に決めなければならない。特に、2日間にわたる場合は土日が丸々つぶれてしまう。
極端な話、東大を受験するのであれば記述型の全国模試を受ける必要はあまりないと思う。医学部志望の生徒や、文系科目に特化して勉強している生徒がいるため、東大志望者全体の中での位置がつかみにくいからだ。
特に社会などでは、東大ではとても出ないような細かい語句を問われることも多い。全国模試での偏差値が低いからといって、必ずしも志望校への合格可能性が低いとは言い切れない。
東京大学の冠模試は、塾にもよるが年3〜5回ほど開催される。駿台だと「東大入試実戦模試」、河合塾だと「東大入試オープン」、東進ハイスクールだと「東大本番レベル模試」などと呼ばれる。
面白いのは成績が返却されるまでの時間だ。前者2つが1カ月〜1カ月半かかるのに対して、東進ハイスクールの返却期間は2週間だ。受験者数が少ないことや採点のシステム化などが要因だとは思うが、その分復習しやすい。
模擬試験を受ける“一番のメリット”
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
各模試で配られる詳細な分析も興味深い。合格者・不合格者は今頃の時期に何点とっていたか、去年の入試における推定の点数分布など、膨大なデータをもとに作られる分析には見入ってしまう。
こういった模試を受ける一番のメリットは、全国のライバルの状態をリアルタイムで把握できたり、最新のテクニカルな受験情報を得られたりする点にある。特に、個別の大学に関する正確な情報や高精度の入試分析は、ネットには出回らないことの方が多い。
例えば東京大学の入試情報は、話題は呼びやすいが、その情報を本気で欲しがっている人はそこまで多くない。ネットで拡散するより、お金をもらって少人数に配布する方が有益なのだ。
高校1年生や高校2年生で初めて模試を受ける時、注意すべきことは、模試に付随してくる講座への勧誘だ。各塾ともに生徒を囲い込むため、たくさんの割引をつけて熱心に入塾を進めてくる。だが、初めて出合った模試を開催している塾が、自分に一番合うとは限らない。
それに、東大専門コースと、個別の校舎では管轄が別の場合がある。個別の校舎の実績を上げるために、あえて校舎の生徒として登録させたがるケースもよく聞く。
パンフレットや塾のスタッフの話をよく精査するのはもちろんのこと、先輩に聞くなどして実際の評判を確かめるのが懸命だ。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







