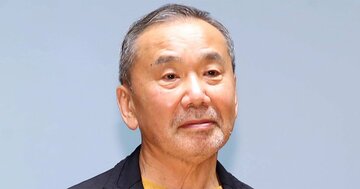自称と対称の両方に「自分」が現れるのでは混乱しそうであるが、自称詞としてはかしこまりモード中心、対称詞としてはくつろぎモード中心なので、案外紛れることはない。
なお、対称詞の「われ」は大変ガラの悪い印象があるが、先ほどの対称詞の「自分」と一部、地域が重なる。「我」は自称詞と反照代名詞に用いられるのであると述べたが、反照代名詞を軸として、自称詞と対称詞は連続していくのである。
つまり、反照代名詞は「(誰かにとって)自分自身」という意味なので、この「誰か」の部分には一人称も二人称も入ることができるということである。例えば「我」は「自称詞―反照代名詞」の両方の用法を持っているが、反照代名詞の用法を通じて、大阪方言では対称詞の用法を得ている。こうして「自分」は、「自称詞―反照代名詞―対称詞」のすべての用法を獲得したわけである。
関西弁→スラング→若者言葉へと
変化し続ける「ワロタ」
「笑う」という動詞は、「笑わない・笑います・笑う・笑えば・笑おう」のように活用するので、学校文法では「アワ行五段活用」と呼ばれる。平安時代ならば、「笑はず・笑ひたり・笑ふ・笑へば」となるので、ハ行四段活用だった。この活用をする動詞には、「言う」「仕舞う」「ふるまう」「買う」「もらう」「味わう」等の多くの項目が含まれる。
このアワ行五段活用動詞に「た」や「て」が付くと、「笑った・笑って」「言った・言って」のように、促音便になる。これに対し、西日本の広い地域では、「笑うた・笑うて」「言うた・言うて」のように、ウ音便となる。さらに関西弁の広い地域で、四拍ウ音便動詞が縮約されて、三拍に発音されるという現象が見られる。
笑う+た → ワロータ → ワロタ
仕舞う+た → シモータ → シモタ
払う+た → ハロータ → ハロタ
だから、「笑ってしまった」は「わろてしもた」になるのだが、これがさらに短くなって「わろてもた」となる。