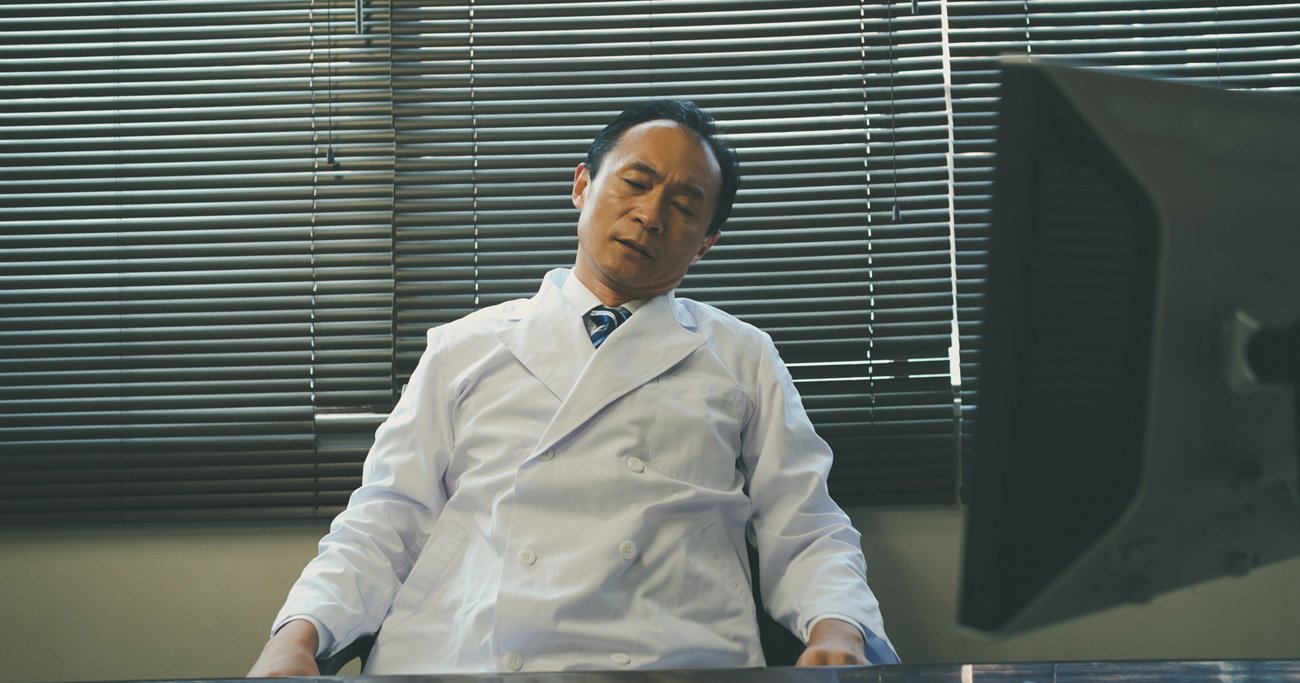 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「誰もが安心して医療を受けられる」ことを掲げ、筆者の祖父が導入に尽力した国民皆保険制度。1961年に導入されたが、その高い理想とは裏腹に、病院はころころ変わる診療報酬に翻弄(ほんろう)されるようになってしまった。理想と現実のはざまで苦境に陥った病院経営のいまに迫る。※本稿は、熊谷賴佳『2030-2040年 医療の真実 下町病院長だから見える医療の末路』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。
孤立無援にあっても
国民皆保険の実現を目指した男
私の祖父である熊谷千代丸は、昭和初期に東京都医師会副会長、旧日本医師会常任理事を務め、1931(昭和6)年頃から国民皆保険制度の導入運動を始めた。
皆保険の導入に積極的だったのは、自分の子どもを3人も病気で立て続けに亡くしたことと関係しているようだ。皆保険制度の導入前は、医療を受けられないために、治療を受ければ助かるような感染症などで命を落とす人も少なくなかった。
しかし、国民皆保険制度が導入されれば、開業医は、それまでたくさん診療費を払ってくれた人に対しても安価な費用で診療しなければならなくなる。そのため、旧日本医師会員の大半は、皆保険制度導入に反対だった。
「誰でも保険を使って一律の料金で治療を受けられるようにすべき」という祖父の思想は、当時、「社会主義者だ」と糾弾された。
確かに、自費診療でやっていれば、裕福な人からは高い診療費が取れる。なぜ安い一律料金で患者をみる必要があるのかと、国民皆保険制度に反対する医師が多いのは、当時としては当然だったのかもしれない。







