厚生労働省は、病院での看取りを減らし医療費を削減するために、在宅医療における訪問診療や看取りの診療報酬を手厚くしたが、その診療内容をチェックする体制やどういう医師が訪問診療をするべきかといった制度は整備されないままになっている。
経験の浅いフリーランス医師が数回訪問して看取っただけで、約10万円の報酬が払われているのを放置したままでよいのだろうか。
例えば総合診療専門医の資格を取得するなど修練を積まないと訪問診療ができないようにするなど、何らかの縛りが必要ではないだろうか。
このままどんな医師でも在宅看取りができるような状態を放置したら、在宅医療は、現代版姥捨て山になりかねない。
患者が死んでくれたほうが
訪問医療医にとって都合がいい
極端な話、昨日までマウスを使った実験ばかりやっていたような医師でも、訪問診療医になれる。在宅医療は、医師が1人で患者の家を訪問するから、ブラックボックスで何をやっているかわからない。
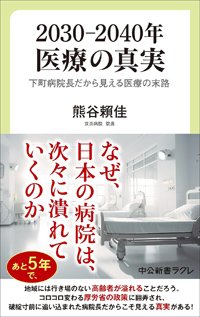 『2030-2040年 医療の真実 下町病院長だから見える医療の末路』(熊谷賴佳、中央公論新社)
『2030-2040年 医療の真実 下町病院長だから見える医療の末路』(熊谷賴佳、中央公論新社)
例えば、患者が肺炎を起こし、入院すれば治るような状態だったとしても、「患者さんが望んでいるんだから、家でみましょう」と言って大した治療もせずに放置し、そのままご臨終になる場合もある。そうなったら看取り収入の10万円が訪問診療の診療所に入る。
家族が救急車を呼んだら、「患者さんが、家で亡くなることを望んでいるのに、なぜ救急車を呼んだんだ」と怒る訪問診療医もいると聞くから恐ろしい。
国は、平均在院日数が長い病院の診療報酬を減らすことで、なるべく高齢者は病院に入院させず、入院した場合には早期退院を促している。
医療費を削減するためにも入院ベッドを減らし、中小病院が潰れてその地域の医療が崩壊しても構わない。高額の診療報酬で誘導する形で在宅看取りを推奨し、自宅で暮らせないなら医療が必要な場合でも介護施設へ送り、それで早く亡くなったとしても寿命だと納得させている。
英国のGPのように診療の質を担保せずに、開業医だけを優遇しているようでは、日本の医療は衰退の一途をたどるのではないかと思えてならない。







