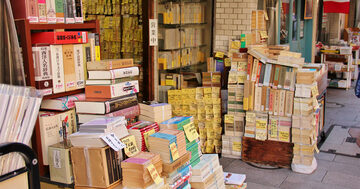写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
疲れていても、時間がなくても、「子どものために」と思って絵本を読み聞かせている親は多いだろう。しかし、「これって、本当に成長につながっているの?」と疑問に思ったことはないだろうか。絵本に登場する言葉が、子どもの語彙力や言語発達にどう影響しているのか。読み聞かせの「目に見えない効果」を、研究データから読み解く。※本稿は、奥村優子『赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか ヒトに備わる驚くべき能力』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
普段の生活で使わない言葉が
絵本では使われている
絵本には、普段の生活ではなかなか出会えない登場人物や出来事がたくさん描かれています。たとえば「おひめさま」や「きょうりゅう」など、日常生活ではあまり使われない言葉を子どもに紹介するきっかけになります。
また、絵本の文章は、普段の会話よりも複雑な構造を持ち、話し言葉では省略されがちな格助詞(「が」「を」など)がしっかり含まれているのが特徴です。そのため、絵本は文法的な側面も含めて、言葉の発達を支える重要な情報源と考えられています。では、実際に絵本には、日常会話と比べて、どのくらい多様な言葉が含まれているのでしょうか。
NTTコミュニケーション科学基礎研究所は、絵本に出現する言葉を詳しく調べるため、「NTT絵本コーパス」を作成しました。これは、絵本の本文をデータ化して、実際に使用されている言語表現を集めて整理したものです。
これまでにも、図書館の蔵書データベースなど、絵本に関するデータベースはいくつか存在していました。しかし、これらは主に書誌情報やあらすじを収録したもので、絵本の本文そのものがデータ化されているわけではありません。NTT絵本コーパスがあれば、どんな言葉がどのような構文で、どれくらいの頻度で使われているかといった、より詳細な分析が可能になります。