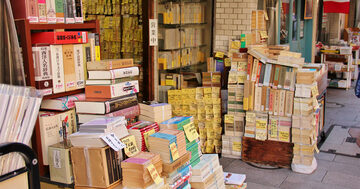後で調べてみると、フィラメントとは「白熱電球などの発熱・発光部分」(大辞林)のことでした。エジソンが白熱電球を開発する際、京都の竹を素材としたフィラメントを使うことで、点灯時間の長い白熱電球の開発に成功したそうです。絵本を通して、親も知らなかった新しい言葉や知識、広い世界に触れる機会が生まれることを実感した出来事でした。
絵本によく出てくる言葉は
子どもも覚えやすい
このように、絵本には多様な言葉が出てくることがわかりました。さらに、私たちは、絵本によく出てくる言葉が子どもの語彙獲得にどのように影響するのかを分析しました(注3)。本文では、その中から動物名と心的状態語について紹介します。
心的状態語とは、「欲しい」「思う」「考える」など、欲求や信念を表す心に関係する言葉です。「ネコ」や「ゾウ」のように具体的な対象を指す名詞とは異なり、心的状態語は抽象的で目に見えないため、子どもにとって理解や習得が難しいとされています。
研究では、0~4歳の子どもを持つ1285名の養育者に協力を依頼し、語彙チェックリストアプリを用いて、子どもが理解・発話している単語を調査しました(注4)。この調査には、心的状態語59語、動物名100語を含む2688語が含まれており、それぞれの語について、50%の子どもが言えるようになる時期(50%到達月齢)を推定しました。
たとえば、動物名では「イヌ」(25.8カ月)、「ダチョウ」(40.0カ月)、心的状態語では「嬉しい」(32.3カ月)、「考える」(38.1カ月)といった獲得時期がわかります。
また、NTT絵本コーパスを用いて、絵本に登場する言葉の出現頻度を解析しました。たとえば、「イヌ」は412冊の絵本に登場し、計1652回出現、「ダチョウ」は20冊で計82回登場しています。心的状態語では、「嬉しい」が777冊で1493回、「考える」が622冊で1601回登場していました。