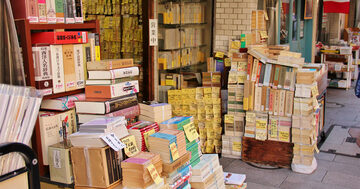語彙獲得時期と絵本での出現頻度の関係を分析した結果、動物名には強い関連がみられました。すなわち、絵本に多く登場する動物名ほど子どもが獲得するのが早く、あまり出てこない動物名ほど獲得するのが遅くなる傾向が確認されました。
心的状態語は登場率に関わらず
子どもには難しいもの
一方、心的状態語については、関連があるものの、動物名と比べると、出現頻度が高くても獲得時期が遅いことがわかりました。
特に、「思う」「考える」「わかる」「知る」などの心的状態語は、頻繁に絵本に登場するにもかかわらず獲得するのが遅く、子どもにとって獲得が難しい語であると考えられます。
これらの結果から、絵本によく出てくる語は子どもの語彙獲得と密接に関係しているものの、心的状態語のような抽象的な言葉は獲得が難しい可能性が示唆されました。
なお、絵本に多く出てくる動物名を絵本コーパスで分析したところ、1位は「ネコ」、2位は「クマ」、3位は「ウサギ」という結果でした。一般的に馴染みのある「イヌ」は9位でした。
絵本の読み聞かせは、子どもが文字に触れる貴重な機会となり、文字の読み書きの学習にも重要な役割を果たします。では、子どもはどのようにして文字を覚えていくのでしょうか。
子どもは自分の名前に含まれるひらがなから興味を持ち始めることが多いといわれていますが、他にどのような特徴が文字習得に関係しているのでしょうか。
子どもには「読める字」と
「書ける字」が存在する
私たちは、ひらがな習得に影響を与える文字の特徴について検証しました(注5)。この研究では、国立国語研究所が行った調査を参照し、4~5歳の子ども2217人を対象としたデータを分析しました。
興味深いことに、子どもが「読める字」と「書ける字」には違いがありました。たとえば、「読める字」のトップ3は「か」「み」「の」でしたが、「書ける字」のトップ3は「し」「い」「こ」でした。