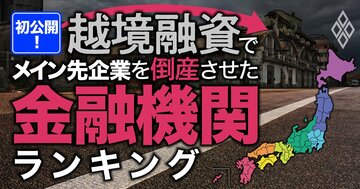語り継がれる「左のポケット」の話
晩年になってもその姿勢は崩れなかった。91歳で会長職を退いた際も「勘ピューターが働かなくなった」と冗談めかして語ったが、根底には数字で物事を見抜く力が衰えたと自覚した冷静な判断があった。
経営に感傷を持ち込まず、数字を基準に退き際まで決断した姿勢は、多くの経営者にとって重い教訓となった。
鈴木氏の経営哲学を象徴する逸話として、多くの人が語り継ぐのが「左のポケット」である。
若くして営業本部長を務めていた頃、鈴木氏は販売店に対して繰り返し次のように説いた(永井隆『軽自動車を作った男 知られざる評伝 鈴木修』プレジデント社)。
《「八百屋のオヤジさんは、二つポケットのあるエプロンをしていた。市場で朝10万円分を仕入れたなら、店を開けて売り上げが10万円になるまでは、右のポケットにだけお金を入れておく。10万円を超えたらはじめて、超えた分を左のポケットに入れるようにする。左のポケットのお金は、パチンコでも何でも自由に使っていい」》
《左のポケットは利益。10万円を超えないのに、何かに使ってしまったなら、翌朝の仕入れができなくなってしまう。売り上げと利益とを、混同してはいけないという戒めである。》
同書には、この比喩が経営者や販売現場に深く印象を残したと記されている。八百屋の日常を例に挙げることで、資金繰りの基本と利益の重みを、複雑な言葉を使わず直感的に理解させる力があった。
単なる節約論ではなく、事業を続けるために何を守り、何を自由に使ってよいかを明確に示したのが「ポケット経営」の核心であった。
これと比較されるのが、稲盛和夫の「アメーバ経営」である。アメーバ経営は組織を細かい単位に分け、それぞれに独立採算を課す方式で、管理会計を駆使して収益や付加価値を数字で把握する。
従業員に経営意識を持たせる狙いが強く、大企業の管理手法として完成度が高い。
だが、制度としては複雑であり、システムや会計知識を前提にしているため、実務に落とし込むには一定のハードルがあろう。