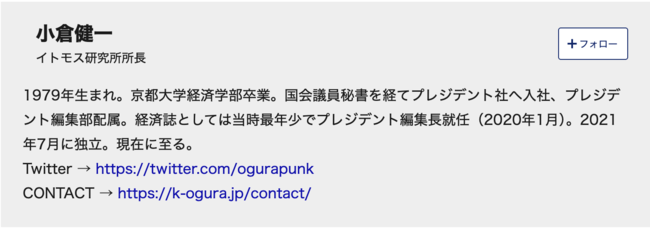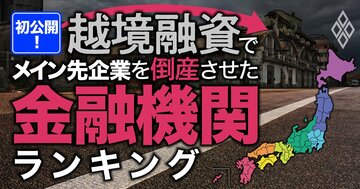豊田章男氏にとっても「憧れのおやじさん」
これに対し、鈴木氏の「ポケット経営」は数字の専門知識を持たない人にも即座に理解できる。右と左のポケットというイメージを通じて、売り上げと利益を混同してはならないという根本を体で覚えさせる。
 Photo:SANKEI
Photo:SANKEI
シンプルであるがゆえに、小さな商店主から大企業の幹部に至るまで同じルールで共有できる普遍性を持っていた。
「ポケット経営」の本質は、資金の流れを単純明快に示すことで無駄な出費や資金繰りの失敗を防ぐ点にある。売り上げはまず仕入れや必要経費をまかなうために存在する。そこからはみ出した分が初めて利益であり、どう使うかは自由だ。
だからこそ鈴木氏は「パチンコでもいい」と冗談めかして語った。冗談の体裁を取りながらも、実際には利益を自由に活用できる境界線を鮮やかに示していた。
要はどちらのポケットに手を入れているかを常に意識することで、経営が安定するという考えであった。
この教えは中小企業や個人商店に限られず、大企業の意思決定にも反映された。低価格戦略で大ヒットした初代アルトの開発でも、まず右のポケットを守る姿勢が貫かれた。
不要な装備を省き、コストを徹底的に削ぎ落とし、原価を確実に回収する。残った左のポケット、すなわち利益を市場開拓や技術導入に投じることで、軽自動車市場に新しい需要を生み出した。
インド進出の挑戦も同じ発想の延長にあった。守るべき資金を守り抜いたうえで、余剰の力を未知の市場に注ぎ込む。単純なルールを徹底したからこそ、スズキは規模で勝る大手メーカーと世界で渡り合えた。
稲盛和夫のアメーバ経営が数字を基盤とした管理会計の体系であるのに対し、鈴木氏のポケット経営は直感的な現金感覚に根ざしている。
どちらも収益を守り抜くという目的は共通しているが、表現方法と浸透力に違いがある。アメーバ経営は組織を動かす制度として優れており、ポケット経営は人の心に残る教訓として力を発揮した。
鈴木氏が94歳で亡くなったとき、トヨタの豊田章男会長は「憧れのおやじさん」と語って追悼した。自らを「中小企業のおやじ」と呼び続けた鈴木氏の姿勢は、無駄を嫌い、利益を守るという現場感覚を生涯にわたって体現していた。
ケチであることを恥じず、誇りとした経営者は少ない。左のポケットに利益を積み上げ続けた人生が、スズキを世界的企業へ押し上げた。ケチ道の権化と呼ばれた所以である彼の教えは今も経営の基本を問い直す力を持ち続けている。