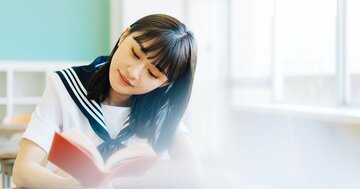1990年代中盤からイオンの出店形態がスーパーのジャスコからショッピングモールへと大型化していくのに合わせ、ブックバーンはロードサイドからモール内への出店に転じる。そして商材も複合型から比較的本にしぼった形態へと転換。もっとも2000年代後半には文具や古本、トレーディングカードなどのホビーとの複合型店舗も増えていく(西尾泰三「書店の発想、小売りの矜持――未来屋書店は電子書籍とこう向き合う」、「ITmedia」2014年8月13日)。
書店がいくら複合化しようが、ワンストップで一通りの買い物ができるショッピングモールのほうがはるかに多種多様な商品・サービスを扱っている。そうなると、わざわざ本だけを目当てに郊外型書店に行く理由は薄れていく。
大店法関連の法律は、日本の書店業にも大きな影響を与えてきた。
複合型書店の衰退を招いた
ストリーミングの衝撃
CD・DVDレンタルやゲームなどの販売との複合型書店は、2010年代以降、急速に色あせていく。Netflixが2015年、Spotifyが2016年に日本に参入。これらのサービスは月1000円程度で多種多様な作品を見放題、聴き放題だった。TSUTAYAやGEOは複数枚をパックでレンタルすると1枚あたり50円とか100円になる「○枚○○円」を打ち出し価格競争に励んでいたが、ストリーミングの登場以降、さらに値下げした。だがそもそものレンタル需要が激減、つぶれるか業態転換する店舗が増えていく。ゲームもダウンロード販売とオンライン上でのセールが登場し、中古ゲーム売買の旨味も減った。
1990年代後半から雑誌が売れなくなって人々の来店回数が減っていった書店業だが、レンタルビジネスがしぼんでいくと、ますます人々は書店に行かなくなった。
郊外型・複合型書店チェーンも、兼業商材の魅力が失われると書店業が儲からず、市場が年々縮小する現実に向き合わざるをえなくなった。1980年代以降、新規出店する書店の坪面積は増え、店の維持にかかる固定費も高くなっていた。だが2000年代以降は1980年代とは異なり「革命」と呼べるほどの新たな魔法の杖は現れず、チェーン書店も撤退していく。