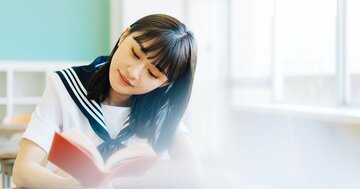書店が“本以外”を扱うのは
生き残りのための選択だった
一方、「町の本屋」に回帰したように市街地に店を構え、坪面積も小さく、固定費を切り詰めた「独立系書店」で「兼業」形態が注目されるようになる。たとえば2012年には内沼晋太郎が東京・下北沢にビール片手に本を選べる書店「B&B(Book&Beer)」をオープンし、毎日イベント開催をウリにした。2016年には東京・荻窪に元リブロ池袋店勤務の辻山良雄によるカフェとギャラリーを併設したTitleが開店した。
 『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』(飯田一史、平凡社)
『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』(飯田一史、平凡社)
チェーン書店も新しい業態を模索する。CCC(当時。現・蔦屋書店)は「森の中の図書館」「大人のTSUTAYA」をコンセプトに、カフェを併設した大型新刊書店・代官山蔦屋書店を2011年に開始。目端の利いたセレクトの本や音楽、しゃれた雰囲気の店で注目を集め、国内30店舗規模に拡大(2025年現在)――もっとも、それをはるかに上回る勢いで全国のTSUTAYAは閉店しつづけている。かつて山ほどCD・ビデオ・DVDを借りた人間としては、さびしいかぎりだ。
兼業書店、複合型書店は1980年代と2010年代に特に注目されたが、いつの時代も書店業単体では儲からず、つねに兼業先が模索されてきた。文具や雑貨を置き、飲食を提供し、イベントに力を入れる形態を「純粋」な本屋ではないとする見方は浅はかだ。専業書店では成り立たない本体価格やマージン設定なのだから、「本のついでに、客単価が高く、粗利の良い別の商材を買ってもらう」兼業書店こそが、まっとうなありようだったとさえ言える。