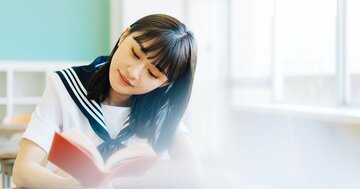しかし、郊外型書店が台頭してくる以前に田舎の住人が日常的に利用していた、10坪から15~16坪の狭い店内に教科書や文具も置いている学校近くの本屋やタバコ屋兼書店などと比べれば、郊外型書店のほうがはるかに品ぞろえがよかった。せまい店の奥あるいは入り口付近で、機嫌の悪そうな中高年の店主がレジに座って立ち読みを監視し、本棚も天井まで届く高さで圧迫感があった「町の本屋」よりも、店内が明るくて広く、中学生でも最上段に手が届く高さの本棚が基本の郊外型書店のほうが、居心地がよかった。
大店法の規制緩和もあり
各地に大型書店が急増
この後、日米構造協議を背景に、大規模小売店舗法(大店法)が規制緩和される。1990年には、大規模店舗の出店の表明から出店勧告までの出店調整期間が上限1年半に短縮される。
また、1994年改正によって、事業者が原則自由に出店できる売場面積が500平方メートル以下(政令指定都市では1500平方メートル以下)から1000平方メートル未満に拡張される。すると全国各地にチェーン書店の大型店舗の出店計画が浮上し、地元書店は危機感を募らせた。
1998年には大規模小売店舗立地法(大店立地法)、中心市街地活性化法、改正都市計画法のいわゆる「まちづくり三法」が成立、2000年には大店法が廃止されて、地域関係者とほとんど対話・交渉なしに大型店舗を設置できるようになった。これによって2020年代現在でも郊外のイメージを形成している、イオンに代表される郊外型ショッピングセンター、ショッピングモールやアウトレットモールなどが誕生する(西田善行「「東京都市圏」の縁をなぞる 国道十六号線と沿線地域の歴史と現状」塚田修一・西田善行編著『国道16号線スタディーズ』青弓社、2018年)。
こうした施設に積極的に出店しているチェーン書店にイオングループの未来屋書店がある。同社はもともと株式会社ブックバーンとして1985年に千葉県千葉市美浜区に誕生し、ジャスコの子会社としてロードサイドに積極的に展開し、全国の書店組合から出店反対運動を起こされていた郊外型・複合型書店の雄だった。