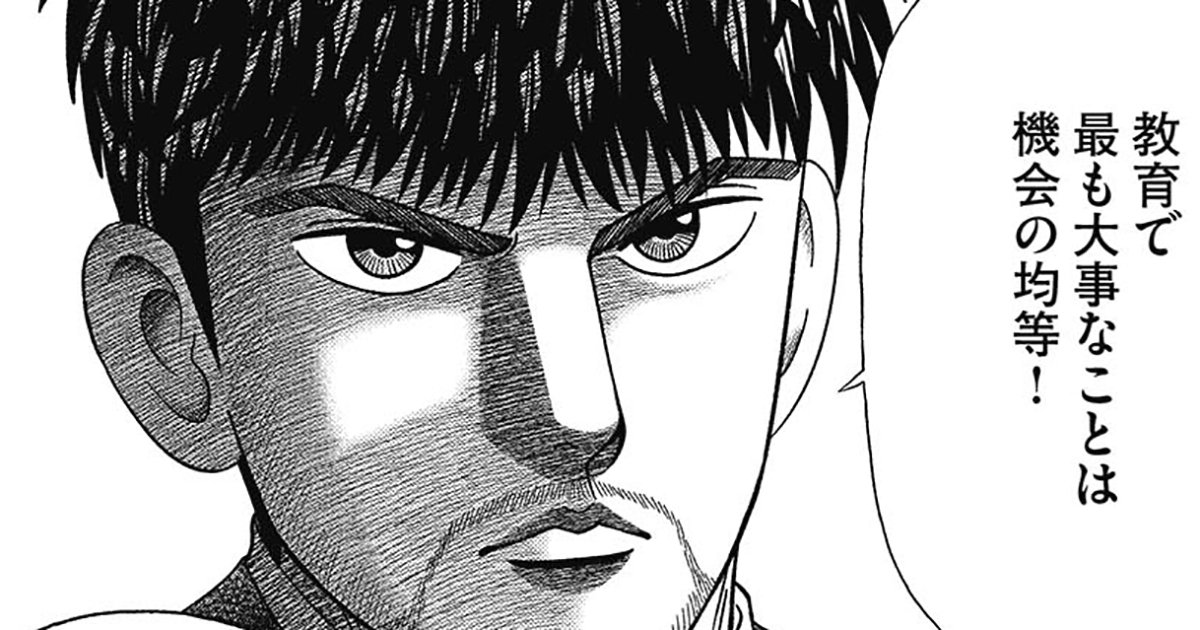 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第99回は、教育における「機会の均等」について考える。
現状の「女子枠」に欠けている視点
龍山高校の改革を巡って、東大合格請負人・桜木建二は理事長代行・龍野久美子と対立していた。アメリカ型の入試がいいという龍野に対して、桜木は「教育で最も大事なことは機会の均等!」と訴える。
教育の持つ機会均等性は、教育基本法にしっかりと明記されている基本中の基本だ。近年たびたび話題になるのが女子枠の設置である。特に理系学部において、男女の進学率・数の差を改善するために、入試に女子専用の枠を設けるという制度である。
世間をにぎわせたのは京都大学や東京工業大学(現在の東京科学大学)が入試に女子枠を設置することを決めた2024年春ごろからだが、国立大学での日本初の事例は1994年度の名古屋工業大学だ。
男子校出身の私は、当初はこの「女子枠」の導入に賛成の立場だった。理系分野に女性が極端に少ない現状は、個人の選択の結果というよりは、社会構造の歪みを反映していると感じていたからだ。
むしろ、男子校にいることで、「女子は社会構造が原因で理系に行きづらい」とひとくくりに考えてしまっていた。
だが、実際に大学に入学し、多様な背景を持つ学生たちと出会う中で、この問題がそう単純ではないことに気づかされた。それは、「属性」で一律に区切ることの危うさだ。
制度によって是正すべき格差は、現行の制度で過不足なく改善できるのか、という疑問が生じてきた。
例えば、極論かもしれないが「地方の公立高校出身で、経済的にも塾に通うのが難しかった男子」と、「都心の裕福な家庭で、中高一貫の私立女子校で手厚い教育を受けてきた女子」を比べた場合、どちらがより「不利」な環境を乗り越えてきただろうか。
現行の「女子枠」は、こうした個別の事情を無視し、「都心の恵まれた女子」を「地方の不利な男子」よりも一律に優遇してしまう結果を招かないか。
制度改善のための「いくつかの方策」
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
もっとも、大学側がこうした批判を承知の上で制度を導入するのには、明確な戦略的理由がある。
最大の論拠は、「ロールモデルの不在」という負の連鎖を断ち切ることだ。現状、工学部などの教授陣や学生が男性ばかりの環境では、女子中高生が将来の自分をイメージしにくい。
まず「枠」を作ってでも女性の数を増やすことで、彼女たちがマイノリティでなくなる環境を作り、それが次の世代の女子学生を引きつける好循環を生む、という「積極的な」狙いだ。
この議論の対立軸は、「機会の均等」と「結果の公平性」のどちらを重視するか、という点にある。残念ながら、両方とも同じくらい重視するというのは難しい。
女子枠なんて絶対になくすべきだ、とは思わない。むしろ「発展的改善」を目指すべきだ。その上で、教育基本法がうたう「機会の均等」をあえて曲げ「公平性」を優先するのだから、この制度には、単なる入試改革以上の徹底した議論と慎重な設計が不可欠だ。
最も重要なのは、目的を明らかにした制度設計だ。何を是正しようとしている制度なのか。制度が助けるべき本当に苦しんでいる層と、結果的に恩恵を受ける層が別々では意味がない。
次に当事者からの意見聴取である。この制度によって不利益を被る可能性のある男子学生、そして「枠」に戸惑う女子学生たちの声にも真摯に耳を傾ける必要がある。
そして最後に長期的な検証が求められる。制度導入によって、その分野を志望する女子学生の総数は本当に増えたのか。あるいはその先、研究職につく割合まで検証する必要があるだろう。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







