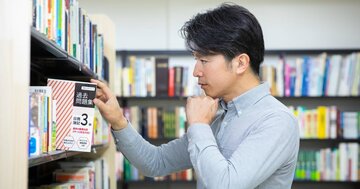人手不足で“傷あり人材”でも採用せざるを得ない事情も
新浪氏のケースだけではありません。数年前から航空会社でパイロットの飲酒が問題になっています。
今年も航空会社でパイロットが会社の運航規程に定める飲酒に係る制限に抵触したとして、国土交通省から厳重注意を受けていました。最終的に企業側が機長を解雇しましたが、再び、別の会社で採用された場合、同じ過ちを繰り返さないとは限りません。
他にも、国土交通省がパイロットに有期の航空業務停止の処分を課して、業務改善命令を出した例もあります。
パイロットの人材不足が深刻な航空業界では、このような“傷あり人材”でも採用せざるを得ない事情があるのでしょう。
“傷あり人材”の雇用にかかわる問題は、大企業に限りません。筆者の周りでも、10年以上も前に小口金庫から数万円を盗んだり、暴力をふるった問題で解雇された人を、どうしても人手不足の小売店の現場で、再雇用した例があります。年数が経過しており、更生している様子もうかがえたため、問題ないと考えたようです。
深刻な人材不足は、さまざまな業界で共通の課題であり、今後もこうした“傷あり人材”を採用せざるを得ない状況が進んでいくと考えられます。
では、そうした人材を採らざるを得ない場合、どうやって再発防止とリスク管理すればいいのでしょうか。企業が取れる対策は、何があるのでしょうか。
「規程」違反は、あくまで会社のルールからの逸脱でしかない
最も身近なところでは、パーパスや就業規則といった「企業独自の規定」があります。
昭和時代に比べると現在は、パワハラ、セクハラも減り、上下関係の厳しい組織文化はよりフラットになっているように見えます。それは、多くの企業が、CSRなどにのっとったコーポレートガバナンスの観点に注目して規定を作っていることも影響しています。
ただし、この効力はあまり強くありません。
人材不足の会社では、問題が発覚し、人事部で問題視されたとしても、それがすぐに解雇につながるわけではなく、厳重注意で済んだり、グループ会社に異動することで守られることもあります。
残念ながら規定は、あくまで社内ルールであり、訴訟問題になった場合でも罰せられないことも多々あるのです。
会社の規程とは、学生の生徒手帳のようなものでしかない企業も多く、規定違反でモラルを欠いた問題を起こしても、法律上大きな問題でない場合、会社は解雇などの処分ができないこともあります。このあたりはケースバイケースで明確ではないことも多いのです。
そのため社内規定の中にルール違反に対する処罰に関して、より明確な部分を増やすことも必要でしょう。
ただし、役員ともなると話は別です。SDGsに逆行する発言や、女性蔑視、様々なモラル違反などで、即解任されることもあります。特にマスコミで取り上げられた場合は、会社のブランド力の低下、株価下落にも悪影響を与えるため、迅速な対応が取られることが増えています。