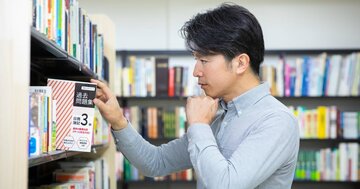投資家対策としてのリスク管理
“傷あり人材”を雇用した場合は、どう管理すればいいのでしょうか。上場している企業などでは、投資家によるチェック効果は期待できるのでしょうか。
実態は、不祥事が発覚し、謝罪会見をした後でも、最悪のケース以外は3~6カ月で株価は元に戻っています。
投資家としてはその間にリスク管理、再発防止対策の方法を追求し続けることに時間を費やすよりも、株価を上げることや、配当金を上げることの方に注力しているのが現実です。
しかしながら投資家は一定のリスク管理には敏感なので、企業は投資家の目を意識して、人材の管理体制について新しいチェック機能を担う担当部署を作ったり、モラル関連の研修を増やしたり、問題に気がついたら相談できる場所を作ったりすることも必要になるでしょう。
多くの企業では、機関投資家との対話やステイクホルダーとの関係を強化する傾向が強まっていることも、こうした対策の追い風となります。
「履歴書」で見抜くことはできない。人権問題にかかわることも
また、企業が、過去に問題を起こした人物と知らずに採用してしまうこともあります。所定の履歴書に賞罰を問う欄がない履歴書もあり、「履歴書には嘘をついてはいけない」という文言があっても、どこまで正直に明記するかは本人に委ねられているからです。
履歴書に記載された過去の勤務先に確認したくとも、個人情報の観点から過去の情報が共有しづらくなっていることも背景にあります。
雇用契約書などに「法律、規定で罰せられた場合、1カ月の告知なしでも解雇できる」などと記している企業はありますが、採用時に面接でしつこく質問することは人権問題にもあたるため、把握することは難しいでしょう。人手不足で採用面接や研修を外部に委託している企業も増えており、よく確認できないといった実態もあります。
過去の問題について寛容になりつつあるのは、人材不足だけが背景ではありません。時間がたてば、問題が起きたことを忘れられて、徐々に復帰すしやすくなる面もあるでしょう。