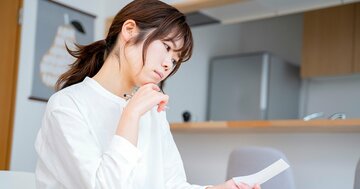たとえ税金を滞納しても
最低生活費からの強制徴収は禁止
国民個人の生活の糧となる「所得」については、このように所得税法が「基礎控除」を定めています。前年の所得に応じて負担する地方税である「住民税」でも、「基礎控除」の定めがあります。
さらに、税金の滞納がある場合に、所有不動産の差し押さえや競売などの強制的な徴収を定めた「国税徴収法」という法律にも、次のような規定があります。国に差し押さえを禁じた財産(差押禁止財産)の規定です。
具体的には、(1)「滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」や、(2)「滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な3月間の食料及び燃料」について、「差し押えることができない。」と定められています(75条1項1号、2号)。
課税そのものの場面ではありませんが、最低生活費からの強制徴収が禁止されています。
このように、憲法が保障する「生存権」は、その「自由権の側面」として、「税制」に対しては「最低生活費非課税の原則」(生活費控除の原則)を求めています。そのことが、「所得税法」にも「地方税法」にも「国税徴収法」にも、明確に反映されているのです。
所得税法の「基礎控除」が定める、「課税されない最低生活費の額」は、国民民主党の主張を踏まえた令和7年(2025年)改正があるまでは、「48万円」だったことになります。ここで、「1年で48万円は、安過ぎるのではないか?」という疑問もあるでしょう。
実際に、こうした所得税法の定める「最低生活費」の「標準額」が低いので、「生存権」侵害ではないかとして起こされた裁判もありました。
しかし、最高裁判所は、「それは立法裁量である」と述べました。「総評サラリーマン税金訴訟」と呼ばれた裁判の判決です。