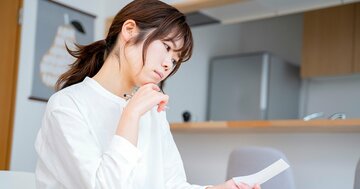写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本では、長年「基礎控除額」が据え置かれ続けてきた。生活費の負担が年々重くなるなか、本来なら憲法が保障すべき「最低限度の生活費」にすら課税される現状が続いている。30年にわたる税制の放置と、失われた30年が同じ“30年”で重なるのは、決して偶然ではない。※本稿は、木山泰嗣『ゼロからわかる日本の所得税制 103万円の壁だけでない問題点』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
30年続いた103万円の壁と
失われた30年の因果関係
2024年10月の衆議院解散による選挙で、「国民の手取りを増やす」と主張した国民民主党が掲げていたのが、「103万円の壁」問題でした。
ここにいう「103万円」は、お金を稼いでも所得税が課されない1年の「課税最低限」でした。暦年課税の所得税で、1年の給与収入が「103万円」までは、所得税が発生しなかったのです。これは、令和7年(2025年)改正前の話です。
その内訳は、次のものでした。(1)「理論的な意味の所得」(理論所得)を計算する際に、給与収入から差し引かれる「給与所得控除額」の「最低保障額」である「55万円」。
そして、(2)「課税の対象になる所得」(課税所得)を計算するために、そこからさらに「所得控除」として「控除」される「基礎控除」の標準額である「48万円」。この2つです。
この2つの額を合計すると、「55万円」+「48万円」=「103万円」になりますから、1年で得た給与収入が103万円までは、「課税所得」が0円になる。結果、所得税も発生しない。これが給与所得者の「課税最低限」でした。