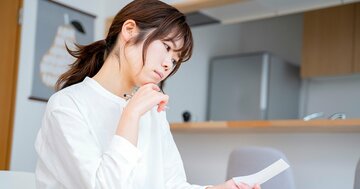「積極的な権利」とは、国民が「国に対して給付などの施策を求める権利」です。いわゆる「社会権」と呼ばれるもので、「国家による自由」といわれます。
しかし、憲法が保障する人権の多くは、思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由など、国から干渉されず、自由でいられる「消極的な権利」を保障しています。いわゆる「自由権」と呼ばれるもので、「国家からの自由」ともいわれます。
最低生活費への課税は
憲法の理念に背いている
日本国憲法25条1項が保障した「生存権」は、最低生活を送るための給付を国に求める「社会権」(積極的な権利、国家による自由)です。これが表向きの保障内容です。
しかし、「最低生活費」にあてざるを得ない費用も含めて、「課税所得」に含める「所得税額の計算」を所得税法が定めるとなれば、どうでしょう?最低生活のためにあてるべき費用が、「利益」(もうけ)から控除されずに課税されることになります。これでは、消極的には「生存権」が侵害されてしまいます。
「社会権」である「生存権」にも、税金を「法律」で定めるときに、国から「最低生活を送る権利」に干渉されない「自由権」(消極的な権利、国家からの自由)の側面があるからです。これを、「生存権」の「自由権の側面」といいます。
日本国憲法25条1項が保障する「生存権」の「自由権の側面」が侵害されることがないよう、所得税法は「課税所得」を計算する際に、「理論所得」から控除する「所得控除」の1つとして、「基礎控除」を定めたのです。
つまり、所得税の「基礎控除」は、国民の最低生活費に課税しないための「控除」なのです。「基礎控除」が、所得税法に定められているのは、憲法で保障された「生存権」を実現するためです。「生存権」の実現には、「税制」で、国民の「最低生活費」に「課税」することがないよう、配慮しなければならないのです。
これを「最低生活費非課税の原則」といいます。この原則は、日本国憲法が保障する生存権の「税制」上のあらわれといえます。専門用語ですが名称が長いので、本記事では「生活費控除の原則」と呼びます。