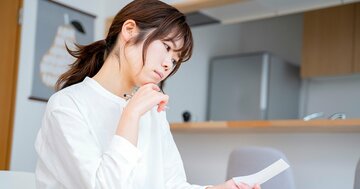国民民主党が提示した問題は、この「103万円」が、令和時代に相応しくないのではないかということでした。というのも、給与所得者に認められてきたこの「課税最低限」である「103万円」という額は、30年間、1度も変わらなかったからです。
これは、ちょうど「失われた30年」といわれる期間にも、重なります。「物価も賃金も上がらないデフレ時代の産物だった」ということです。
そもそも基礎控除は
生存権を保障するための制度
経済はわたしの専門ではありませんが、マクロ経済学の専門家の著書に、「1995年あたりから……日本の物価と賃金は上昇をやめ、毎年据え置かれるようになった」との記述があります(渡辺努『物価を考える』〔日本経済新聞出版、2024年〕21‐23頁)。
「103万円」になったのが、くしくも同じ1995年(平成7年)なのです。しかし、いまの日本では、物価上昇が年々進んでいます。わたしたちが日々、生活のために支払う「物の値段」は上昇していますよね。
では、そもそも「基礎控除」は、何のためにあるのでしょうか?所得税の「基礎控除」は、「国民の日々の生活にかかる費用には、課税すべきではない」という考え方によるものなのです。
これは、「憲法上の要請」になります。
日本国憲法25条1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められているからです。いわゆる「生存権」を保障した規定です。
つまり、「すべて」の「国民」には、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障されています。ここにいう「健康で文化的な最低限度の生活」を「最低生活」と呼びます。
もし、「最低生活」にかかる費用(最低生活費)も、「課税所得」に含めて「所得税の額」を計算するとなれば、憲法で保障された「生存権」が侵害されてしまいます。
「生存権」は、本来的には「最低生活」を送ることができるよう、国に求める「積極的な権利」です。「生活保護」などの社会保障を、国は充実させるべきということです。