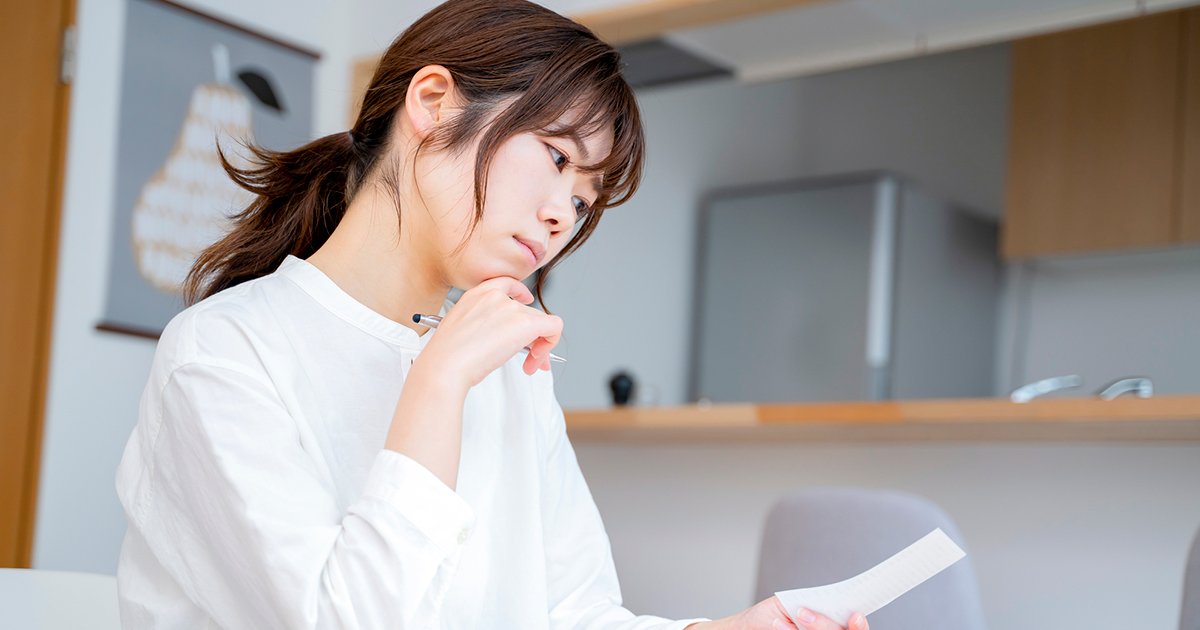 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
勤め先の賃上げが進んでいるはずなのに、なぜか手取りが増えた実感がない――。その背景にあるのが、税率を見直さないまま放置されている所得税制だ。危ぶまれる「ブラケット・クリープ」の問題と、今の日本政府が取るべき動きについて考えていく。※本稿は、木山泰嗣『ゼロからわかる日本の所得税制 103万円の壁だけでない問題点』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
所得税率を放置していたら
それだけで国民の負担増になる
「所得の再分配」という「機能」が、「所得税法」で本来発揮される場面は、「累進税率」になります。担税力に応じて、税負担を行うべきという「応能負担原則」は、所得税、相続税、贈与税に顕著にあらわれています。
これに対して、「能力」(担税力)にかかわらず、「行政サービス」という利益を享受することを前提に課税する考え方もあります。「応益課税」と呼ばれるものです。地方税では、「応益課税」の発想が強いといわれています。
「応能負担原則」を求める「所得税制」は、「垂直的公平」(編集部注/所得の高い人に大きな税負担を求める公平性)を実現するものということもできます。
「消費税」(10%。ただし、8%の軽減税率あり)や、「法人税」(原則23.2%)が、一定の比の税率である「比例税率」で「税率」が動かないのは、これらの税金が「水平的公平」(編集部注/課税の対象の額の高低にかかわらず、税率を同じにする公平性)を実現しようとしているからです。これらの税金と「所得税」は、異なるのです。







