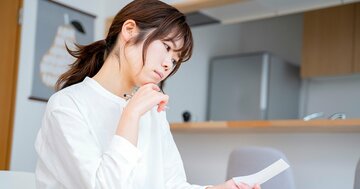選挙で民意を示した結果
30年不変の税制が動いた
 『ゼロからわかる日本の所得税制 103万円の壁だけでない問題点』(木山泰嗣、光文社)
『ゼロからわかる日本の所得税制 103万円の壁だけでない問題点』(木山泰嗣、光文社)
租税法律主義(編集部注/税金は、法律に基づかなければ課すことができないという原則)のもとでは、あくまで「税制」は、主権者である国民が選挙で1票を投じた国会議員が「全国民の代表者」として、国会で議論して定めます。
「立法裁量」というのは、税制は(三権のうち「立法」を担う)国会で定めるべきものであり、(三権のうち「司法」を担う)裁判所は、これに干渉するのを原則として差し控えるということです。
「三権分立」の発想ですね。三権分立とは、国家権力を「立法」「行政」「司法」の三権に分けることで、権力の抑制・均衡を図る「権力分立」のことです。ただし、立法に明らかな「逸脱・濫用」があるような場合には、裁判所も乗り込みますけどね、ということも最高裁は述べていました。以下に、引用しておきましょう。
「……憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない(略)。」
(最判平成元年2月7日判タ698号128頁)
(最判平成元年2月7日判タ698号128頁)
平成元年(1989年)に下された最高裁判決は、税制の内容として「生活費控除の原則」としての基礎控除の標準額をいくらと定めるかについては、そのときの状況に応じて、法改正で対応すべきというメッセージを送りました。
実際、「税制」は、毎年「改正」されています。
だからこそ、令和7年(2025年)の「税制改正」に向けて国民民主党は、選挙の際に具体的な主張を行ったということです。そして、そこで一定の民意を得たことから、政権与党である自民党・公明党も、その主張の一部を受け入れることになりました。
これが、「税法学」からみた、「103万円の壁」問題の流れになります。