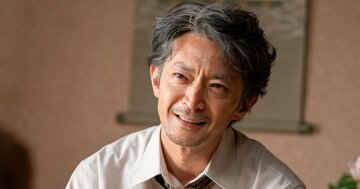はりきって、『詩とメルヘン』に連載したものの……
意外なアンパンマンの応援者は八木だった。
八木が嵩に『詩とメルヘン』に『アンパンマン』を連載するように提案する。
嵩はやる気になって、再び、大人向けに『怪傑アンパンマン』を書き始める。また片仮名に戻っている。今度は、ヤルセ・ナカスという漫画家とミテ・ミルカという編集者が登場する。次々とアイデアやキャラが思いつくのが嵩(やなせたかし)の才能である。
八木はなぜ『アンパンマン』を応援するのか。就業前の児童に人気であるのだから商機があると踏んで、できるだけ広げておこうと考えたようなのだ。
いつの間にか「商業主義者」になっている八木。ビジネスを拡大しながら、自身の理念や哲学をさりげなくビジネスのなかに込めて広げようという戦略のようである。八木のモデルはサンリオの創業者・辻信太郎で、サンリオがまさにハートフルな感覚をキャラクタービジネスにした企業であった。
八木の話を聞く蘭子。一時期、葛藤があったものの、最近はキューリオに当たり前に出入りして、八木とも平然と近い距離で接している。これが大人の空気感ってことだろうか。
はりきって「熱血メルヘン『怪傑アンパンマン』」を書いたものの、結局これもあまり人気が出ないまま連載終了となった。
嵩が若き頃、影響を受けたフランケンシュタインのようなゴシックホラー的な雰囲気もあったり、商業主義の企業家が出てきたり、売れて志が変わってしまう漫画家がいたり。資本主義が必ずしもいいことではないというようなメッセージ性が感じられる。
蘭子が「おしつけがましい」と以前批評していたが、確かに嵩のモデル・やなせたかしの書くものはメッセージ性、テーマ性が強すぎるきらいも感じる。「怪傑アンパンマン」は案の定、あまりヒットしなかった。
蘭子じゃないが辛口で感想を述べると、テーマ性――逆転しない正義を謳いながら、「熱血」とか「怪傑」とかいうワードを付していることに矛盾を感じる。売れるためにちょっと工夫しているのかもしれないが。あと、やっぱり、片仮名にしたり平仮名にしたりして混乱を招く。モデルのやなせたかしは、ひじょうに定まらない人なのだと感じる。彼がなかなか売れなかったのは、こういうところではないか。知らんけど。
でもまた彼(嵩)に手が差し伸べられる。