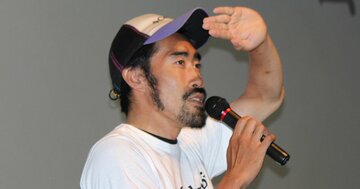「難しいですね。オーストラリアに行くしかないでしょう」。
その時はそう答えた。
「脳死を人の死」とすることへの見解が割れていた当時、日本で脳死移植は制度化されておらず、現実的でなかった。生体移植でも肝臓は技術的に難しかった。
1988年12月に一例目がブラジルで実施され、89年7月に同国で2例目、オーストラリアで例目と続いたが、1、2例目は手術直後に患者が死亡するなど、「失敗」とみなされていた。
山口県和木町の開業医だった木村さんが、生後間もない杉本裕弥ちゃんを初めて診察したのは、88年12月。先天性胆道閉鎖症とみて、地元の国立病院での受診を勧めた。
そこで受けた2度の手術は効果がなかった。「余命は半年、長くても10カ月」と告げられ、西日本の有名な病院を回っても状況は変わらない。
家族は、父の明弘さんの肝臓の一部を移植する手術を望んだ。「俺が助けるから」。明弘さんは酒を控え、手術に備えた。母の寿美子さんは「子供が死んでいくのを黙って見ていられなかった。あきらめたくなかった」と話す。裕弥ちゃんは2人にとって初めての子供だった。
兄への贖罪もこめて
「何としても人命を救いたい」
「とにかく一度診てほしい」。再度頼まれた永末さんは、岩国市内の病院で裕弥ちゃんと対面した。黄疸(おうだん)があり、腹部は腹水でぱんぱんに膨れていた。「いつ亡くなってもおかしくない」と感じた。
「このままでは悔いが残る。結果は問いません」。家族の切実な思いに心を動かされ、自問した。
「自分はなぜ医師になったのか」
小学5年の時、不幸な事故を経験した。近所の池に飛び込み、浮かび上がった瞬間、続いて飛び込んできた3つ上の兄と頭がぶつかった。脳しんとうを起こした兄は池に沈み、息絶えた。
「ずっと罪悪感があった。兄の分も生きて、人の命を救う仕事に就きたいと思うようになった」。