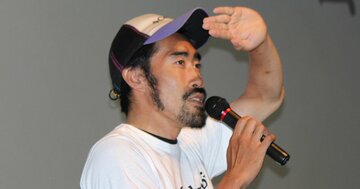写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
1989年、日本初となる生体肝移植に踏み切った外科医がいた。技術的にも倫理的も難しいと言われる中、「助けたい」という家族の願いに応える形で手術は実施された。以来、日本での生体肝移植は累計1万件を越えている。移植医療を大きく変えた、あのときの彼の〈決断〉に迫る。※本稿は、読売新聞社会部「あれから」取材班『「まさか」の人生』(新潮社)の一部を抜粋・編集したものです。
命を救うため日本初の
肝移植を〈決断〉した外科医
腹水で膨れ上がった腹部にメスを入れた。普段はアレルギー対策でゴム手袋の内側にはめる布手袋は、あえてしなかった。指先の感覚を少しでも研ぎ澄ませたかった。やたらと喉が渇き、マスクの下から何度も水を飲んだ。
1989年11月13日、島根医科大学(現・島根大学医学部)の助教授だった永末直文さん(当時47歳)は、1歳の男児に切り取った父親の肝臓の一部を移植する手術に臨んだ。日本初の生体肝移植。世界でも4例目だった。
男児は、肝臓から腸へ胆汁を送り出す胆管が生まれつき機能しない「先天性胆道閉鎖症」。移植以外に助かる道はない。家族の切実な思いと、「自分が逃げたら日本では当分できない」との使命感に突き動かされた。
15時間45分に及んだ手術は無事終わった。自然と湧き上がる拍手にも、気を緩めなかった。
――――電話口の声は張り詰めていた。89年9月中旬、永末さんは、大学内の部屋で1本の電話を受けた。
「生体肝移植が必要な子がいる。君にしか頼めない」。
かつて勤務した広島赤十字病院(現・広島赤十字・原爆病院)の同僚、木村直躬さんだった。