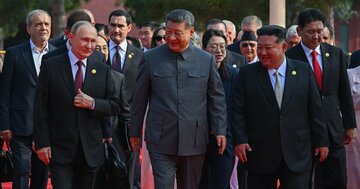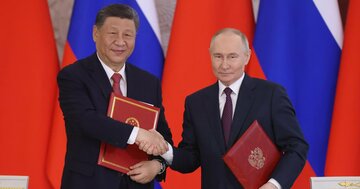分厚い外貨準備と
高水準の家計貯蓄
中国経済が崩壊に至らない最大の理由として、外貨準備と家計貯蓄が中国の財政にとって強固な防波堤になっていることがある。
2025年7月時点で、中国の外貨準備高は約3.3兆ドルに達しており、世界最大規模を維持している。
https://tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves
中国政府は、中国経済が二桁成長を遂げていた時期であっても、人民への社会保障を充実させず、その財政をもっぱら「さらなる経済成長」と「国際覇権の拡大」と「治安維持」に当ててきた。
これはいわば、多くの人民の負担の上に国家の威信を拡大するという構図である。これは、都市戸籍と農村戸籍を分け、「身分」を固定化して、多くの貧困層から搾取が可能なシステムによって維持されてきた。
社会保障が貧弱である代償として、多くの人民が貯蓄に励み、内需が拡大せず、輸出だけが肥大化することによって外貨準備が積み上がった。
この潤沢な外貨準備は、アジア通貨危機やラテンアメリカの債務危機で見られた「ドル不足→通貨暴落→金融破綻」という連鎖を防ぐ盾となっている。
通常の国であれば「破綻状態」であっても、中国経済は破綻せず維持される構造を有している。
とくに、内需拡大に力を入れず輸出主導であったことで、経常収支は恒常的に黒字であり、いまだに外貨の蓄積は安定的に続いている。
また、中国の家計は突出して高い貯蓄率を誇る。J.P.モルガンの推計によれば、2023年の家計貯蓄率は31.7%に達し、2022年には一人あたり貯蓄率が34.3%と過去十年で最高を記録した。
https://am.jpmorgan.com/au/en/asset-management/adv/insights/market-insights/market-updates/on-the-minds-of-investors/a-dive-into-chinese-households-balance-sheets/
中国における家計の高貯蓄は、医療・教育・老後資金を自前で賄わねばならない社会保障への不安から来ている。中国の消費は伸び悩んでいるが、その裏返しとして極端な消費崩壊や資金流出を防ぐ「安全弁」として機能している。
これは日本のデフレ期に起きた構図とは逆である。
日本ではバブル崩壊後、多くの都市不動産の所有者が含み損を抱え、年配者層以外の家計貯蓄率が低下し、所得の伸び悩みや雇用不安と相まって消費が縮小し、長期のデフレ不況を形成した。
中国の場合は、むしろ貯蓄率が高すぎることが消費を抑制し、内需拡大の妨げになっている。
ただし、人民が政府への不信感を深めれば「タンス預金化」して、経済にとってマイナスになる可能性がある。今はその瀬戸際にあり、今後も現在の体制を維持できるかは不透明だ。