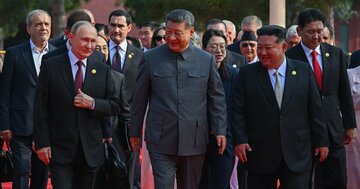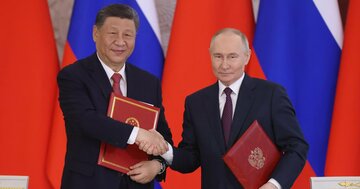日本のバブル崩壊後とは対照的な
国家資本主義による「経済管理」
「分厚い外貨準備」と「高水準の家計貯蓄」以外の中国経済の特徴として、中国特有の国家資本主義体制がある。
政府は毎年「目標成長率」を掲げ、それに合わせる形で政策と統計を調整する。国有銀行が金融システムの中枢を占めるため、地方政府や不動産企業が巨額の債務を抱えても、政府の指示で借り換えや再編が行われ、破綻が回避される。今の中国経済はこれを繰り返している。
この点も、日本のバブル崩壊後とは対照的だ。
日本では不良債権処理が遅れ、民間銀行が貸し渋りや貸しはがしを行い、企業倒産の連鎖を招いた。中国の金融機関では「貸さない」のではなく、「貸し続ける」ことで延命させており、信用収縮による金融危機をなんとか回避し続けている。
もちろん、これらの企業は健全ではなく、多くが「ゾンビ企業」である。ゾンビ企業を温存し続ければ、それだけ中国企業全体の生産性は下がり、経済全体が停滞する。
ただし、潰れかけている企業を速やかに手当てしていくことは、連鎖倒産を防ぐ点では有効だ。これも中国経済の急激な崩壊を防ぐ防護壁となっている。
中国政府は、雇用の維持を最優先課題としている。特に国有企業を通じて雇用が守られることは、大規模失業が社会不安に転化するのを防いでいる。アメリカによる高関税政策によって外資の一部は撤退し、その規模は縮小しているが、それでも依然として中国は「世界の工場」としての地位を保っている。
統制によって崩壊を回避するという中国のモデルは、まさに国家資本主義の典型だろう。ただし、それらが「持続可能」なのかどうかは、今後の経済活動次第だ。
製造業の底堅さと
「世界の工場」の持続力
中国経済を支える大きな要因の一つが、依然として強固な製造業である。
第一に、サプライチェーンの集積度である。電子部品から繊維、化学、機械まで、川上から川下までの産業集積が中国国内に形成されており、代替国にすげ替えるのは決してたやすくはない。
アメリカや日本、東南アジアへの生産分散はたしかに進んでいるのだが、完成品組み立てから部材供給までを一国でこなせる体制は依然として中国が群を抜いている。