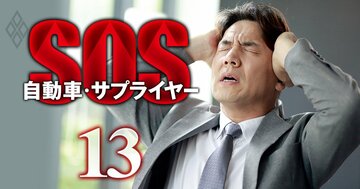Photo:Bill Pugliano, Bloomberg, SOPA Images/gettyimages
Photo:Bill Pugliano, Bloomberg, SOPA Images/gettyimages
日経平均株価が最高値を更新する中、存在感を発揮できていない自動車部品セクター。CASEやマクロ環境の変化への対応など中長期的な課題は多いが、ここにきて「世界的なEVシフトの軌道修正」が明らかになりつつある。果たして日本企業はこの好機を生かすことができるのか。特集『5年後の業界地図2025-2030 序列・年収・就職・株価…』の#57では、EVシフトが進んでも強い企業やこのままでは失速しかねない企業について分析。さらには、時価総額の上位企業同士であってもM&Aを検討した方がいいケースや、新領域に活路を見いだした企業についても具体名を挙げて解説する。(ダイヤモンド編集部 篭島裕亮)
悲観論が強かった自動車部品セクターだが
今後5年間は業績も株価もTOPIXを上回る?
日経平均株価の最高値更新をけん引した半導体や金融と比較して、株価の出遅れ感が強いのが自動車部品セクターである。2024年初から25年9月12日まで日経平均が34%上昇している中、自動車部品が属する輸送用機器セクターは11%の上昇にとどまっている。
全体相場が高値圏にある中でも、依然としてPBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業も目立つ。端的に言えば、成長性が乏しいセクターだとみられているのだ。
詳しくは後述するが、自動車部品メーカーはCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング/サービス、電動化)対応を迫られている。そして最大の問題は、日本の自動車部品メーカーの中でCASEが追い風となる企業が少ないことだ。
米トランプ政権の誕生後、急速なEV(電気自動車)化にブレーキがかかっていることは、ガソリン車に強い日本企業には朗報ではある。だが、それでもEV化の大きな流れは変わらないという見方が一般的だ。
「中長期的には電動化や自動化が進むだけでなく、自動車が個人保有の消費財から共有インフラに変化していく。台数を売るだけで成長する会社は難しくなり、付加価値を中心に捉えた成長を目指していかないといけない。方向性は大きく二つ考えられ、培った技術を生かして車以外の領域に進出するか、さらに付加価値を高めるかだろう」(東海東京インテリジェンス・ラボの金井健司シニアアナリスト)
中長期の明るい材料が少ないように見える自動車部品セクター。中国企業の台頭、円高などリスク要因を挙げると切りがないが、このまま沈んでしまうのか。
だが、意外にも金井氏は今後3~5年の自動車部品セクターについて強気で見ている。金井氏は「個別性が高い業界である」と前置きをしつつ、30年までという時間軸で自動車部品セクター全体を見ると「業績、株価共にTOPIX(東証株価指数)以上のリターンが期待できる」と分析する。
金井氏が「3~5年は業績、株価共に強気」と語る根拠は何か。
次ページでは自動車部品セクターを強気で見る理由に加えて、時価総額の上位企業同士であってもM&Aを検討した方がいいケースなど、10年先を見据えた自動車業界の課題を分析。意外な理由で飛躍が期待できる企業についても具体名を挙げて解説する。