篭島裕亮
#26
進学実績が復活傾向にある東京、神奈川の公立高校だが、「東京一科」への現役実進学率が高い最強の公立高校はどこか。本稿では、他のメディアで多用される延べではなく、本当の進学力が分かる「重複なし&現役で進学」した生徒の割合を示す「公立高校【東京一科】現役実進学率ランキング」を作成した。東京一科に加えて、「東京一科+旧帝大+早慶」など各大学群への現役実進学率や、GMARCHなどを含めた全28大学への進学者数など詳細データも付けた。わが子に公立高校に進学してほしいという家庭はもちろん、中学受験をさせるか悩んでいる家庭もぜひ学校選びの参考にしてほしい。

#25
日比谷、北野、札幌南、仙台第二、浦和、岡崎、小石川…、「東京一科+旧帝大+早慶」への現役実進学率が高い最強の公立高校はどこか。首都圏では中学受験ブームが継続しているが、難関大学進学を意識する場合でも、全国的には高校受験ルートが王道になる。そこで本稿では、他のメディアで多用される延べ合格者数ではなく、本当の進学力が分かる「重複なし&現役で進学」した生徒の割合を示す「全国・公立高校【東京一科+旧帝大+早慶】現役実進学率ランキング267」を作成した。各大学への現役実進学者数など詳細データも付けたので学校選びの参考にしてほしい。

#24
中学受験の4教科で最も点数差がつき、最も成績に悩む子が多いといわれる科目が「算数」だ。「先取り」を武器にして、塾生の83%が御三家・早慶以上に進学した「フォトン算数クラブ」の武井信達塾長に算数力を伸ばす秘訣を聞いた。難関校志望者向けはもちろん、算数偏差値40台の子を1年で偏差値10アップさせる勉強術や、注目度が高まっているオンライン学習の効果的な取り組み方についても開陳する。

#13
「中堅校」人気が加速している。中高の6年間を通じて「わが子が伸びる」という視点で学校選びをする保護者が増加しているからだ。とはいえ、中堅校は御三家や早慶付属と比較して情報が少なく、学校選びが難しい。そこで本記事ではプロ5人が厳選した「偏差値30台、40台から狙えるお薦めの23校」を一挙に紹介する。中堅校は改革意識が強く、「面倒見の良い」学校が多い。学校のタイプも共学、別学、大学付属、国際系…などがそろうので本命校候補としても併願校候補としてもチェックしてほしい。
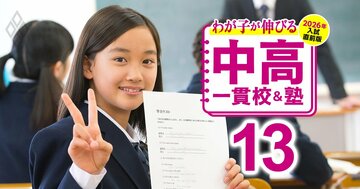
2025年の日経平均株価は10月末に史上最高値を付けて以降、値動きの荒い展開が続いている。「高市政権の政策」「米国の利下げ」「AI投資」など強弱材料が混在する中、日本株は強さを発揮できるのか。専門家8人に2026年の日本株の見通しを聞いた。

アナリスト予想を活用して、来期以降も業績の拡大が期待できる中長期保有向けの「お宝株」候補440銘柄をリストアップした。後編では、「割安株」「高配当株」「成長株」の三つのランキングと計240銘柄を一挙に公開する。下値リスクが小さい「割安株」、利回り狙いの「高配当株」、急成長企業がそろう「売上高拡大株」とそれぞれ強みが違うので、銘柄を組み合わせてポートフォリオを作ることもお勧めだ。日経平均株価が高値圏にあるときこそ、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、業績の裏付けのある銘柄をセレクトしよう。

日経平均株価が高値圏にあるときこそ、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、業績の裏付けのある銘柄をセレクトしたい。本稿では、アナリスト予想を活用して、来期以降も業績の拡大が期待できる中長期保有向けの4種類の「お年玉株」候補をリストアップした。前編では「3期先に利益が伸びる」200銘柄を紹介する。

#21
関西の最難関国立大学群である「京阪神(京都大学、大阪大学、神戸大学)」への現役進学率が高い高校はどこか。本特集では全国4300校を対象とした大学通信の調査を基に、実際に重複なしで何パーセントの生徒が現役でどの大学群に進学したかが分かる「現役実進学率ランキング」を作成。今回は「京阪神・現役実進学率ランキング」を紹介する。中高一貫校が上位を占める「東京一科」とは異なり、「京阪神」は公立名門校が強さを見せる格好となったが、果たして上位の顔触れは?「京阪神+東大」や「関関同立」への現役実進学率、各大学への現役実進学者数など詳細データも付けたので学校選びの参考にしてほしい。

難関私立大学群である「GMARCH」の現役実進学率が高い中高一貫校はどこか。大学合格実績は既卒生も含めた「延べ合格者数」が使われるのが一般的だが、この場合、既卒生や一部の優秀な生徒が合格者数を稼ぐケースもある。そこで本特集では大学通信の調査を基に、実際に重複なしで何パーセントの生徒が現役でどの大学群に進学したかが分かる「現役実進学率ランキング」を作成した。今回は「GMARCH」への現役実進学率ランキングを公開する。「GMARCH+早慶上理以上」の現役実進学率や、各大学への現役実進学者数など詳細データも付けたので学校選びの参考にしてほしい。

#18
中学受験の大手四大塾の一つであり、中堅校を中心に高い合格実績を誇る日能研。特徴は「子どもの学びを真ん中に」という方針で、中学入学後の「後伸び」に定評がある。茂呂真理子取締役副社長にライバル塾との違いや、近年の「パターン学習&圧倒的な物量」の学習スタイルに警鐘を鳴らす理由、高みを目指す子どもを選抜した「グランドマスタークラス」を新規開講する背景について聞いた。

#14
社会の変化により、理系人材が脚光を浴びている。そこで今回は国立大学4校(東京農工大学、東京海洋大学、電気通信大学、名古屋工業大学)、東京理工系4大学(工学院大学、芝浦工業大学、東京電機大学、東京都市大学)、東京農業大学、豊田工業大学への中高一貫校・合格率ランキングを作成。各大学の合格者数内訳に加えて、早慶理系学部への合格率など詳細データも完全公開する。

#5
私立大学の最難関群である「早慶上理」の現役実進学率が高い中高一貫校はどこか。大学合格実績は既卒生も含めた「延べ合格者数」が使われるのが一般的だが、この場合、既卒生や一部の優秀な生徒が合格者数を稼ぐケースもある。そこで本特集では大学通信の調査を基に、実際に重複なしで何パーセントの生徒が現役でどの大学群に進学したかが分かる「現役実進学率ランキング」を作成した。今回は「早慶上理」への現役実進学率ランキングを公開する。ランキングには御三家から偏差値50前後まで幅広い学校が登場する。「東京一科+早慶上理」の現役実進学率や、各大学への現役実進学者数など詳細データも付けたので学校選びの参考にしてほしい。

#13
「中堅校」人気が加速している。中高の6年間を通じて「わが子が伸びる」という視点で学校選びをする保護者が増加しているからだ。とはいえ、中堅校は御三家や早慶付属と比較して情報が少なく、学校選びが難しい。そこで本記事ではプロ5人が厳選した「偏差値30台、40台から狙えるお薦めの23校」を一挙に紹介する。中堅校は改革意識が強く、「面倒見の良い」学校が多い。学校のタイプも共学、別学、大学付属、国際系…などがそろうので本命校候補としても併願校候補としてもチェックしてほしい。
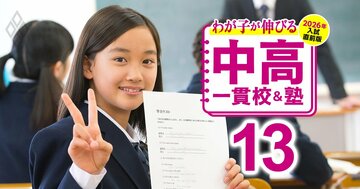
#11
関西の難関私立大学群である「関関同立」の現役実進学率が高い中高一貫校はどこか。大学合格実績は既卒生も含めた「延べ合格者数」が使われるのが一般的だが、この場合、既卒生や一部の優秀な生徒が合格者数を稼ぐケースもある。そこで本特集では大学通信の調査を基に、実際に重複なしで何パーセントの生徒が現役でどの大学群に進学したかが分かる「現役実進学率ランキング」を作成した。今回は「関関同立」への現役実進学率ランキングを公開する。京都大学、大阪大学、神戸大学なども含む「関関同立以上」の現役実進学率や、各大学への現役実進学者数など詳細データも付けたので学校選びの参考にしてほしい。

#10
大学受験で「理高文低」の時代が続いている。社会の変化により、理系人材が脚光を浴びているからだ。では、最難関である東京大学、京都大学の「理系学部」に強い中高一貫校はどこか。今回のランキングでは、「東大+京大」の理系学部の合格率に加えて、旧帝大の理系学部の合格者数内訳など詳細データも完全公開する。

#8
慶應、慈恵、日本医科、順天堂など「私立大学の医学部」の合格者が多い中高一貫校はどこか。今回のランキングでは、私立大学医学部の合格者総数に加えて、全32大学の合格者数の内訳や中学入学時偏差値など詳細データも完全公開する。私立大学の医学部は親世代と比較して難化しており、合格者数の上位には名門中高一貫校が並ぶ。果たしてその顔触れは?

#7
大学入試の最難関学部である「国公立大学の医学部」の合格者が多い中高一貫校はどこか。高い学力が必要になるだけに合格者数の上位には名門中高一貫校が並ぶが、特徴は「首都圏以外」の中高一貫校の医学部志向の強さだ。上位10校の中で9校が首都圏以外の中高一貫校となったが、果たしてその顔触れは?今回は国公立大学の医学部の合格者総数に加えて、全50大学の合格者数など詳細データも完全公開。中学入学時偏差値も付けたので学校選びの参考にしてほしい。

#6
難関私立大学群である「GMARCH」の現役実進学率が高い中高一貫校はどこか。大学合格実績は既卒生も含めた「延べ合格者数」が使われるのが一般的だが、この場合、既卒生や一部の優秀な生徒が合格者数を稼ぐケースもある。そこで本特集では大学通信の調査を基に、実際に重複なしで何パーセントの生徒が現役でどの大学群に進学したかが分かる「現役実進学率ランキング」を作成した。今回は「GMARCH」への現役実進学率ランキングを公開する。「GMARCH+早慶上理以上」の現役実進学率や、各大学への現役実進学者数など詳細データも付けたので学校選びの参考にしてほしい。

#5
私立大学の最難関群である「早慶上理」の現役実進学率が高い中高一貫校はどこか。大学合格実績は既卒生も含めた「延べ合格者数」が使われるのが一般的だが、この場合、既卒生や一部の優秀な生徒が合格者数を稼ぐケースもある。そこで本特集では大学通信の調査を基に、実際に重複なしで何パーセントの生徒が現役でどの大学群に進学したかが分かる「現役実進学率ランキング」を作成した。今回は「早慶上理」への現役実進学率ランキングを公開する。ランキングには御三家から偏差値50前後まで幅広い学校が登場する。「東京一科+早慶上理」の現役実進学率や、各大学への現役実進学者数など詳細データも付けたので学校選びの参考にしてほしい。

#4
筑駒、灘、開成、日比谷……、最難関大学群である「東京一科」への現役進学率が高い高校はどこか。大学合格実績は既卒生も含めた「延べ合格者数」が使われるのが一般的だが、この場合、既卒生や一部の優秀な生徒が合格者数を稼ぐケースもある。そこで本特集では全国4300校を対象とした大学通信の調査を基に、実際に重複なしで何パーセントの生徒が現役でどの大学群に進学したかが分かる「現役実進学率ランキング」を作成した。初回は最難関の「東京一科」への現役実進学率ランキングを公開する。「東京一科+旧帝大」「東京一科+旧帝大+早慶」の現役進学率や、各大学への進学者数など詳細データも付けたので学校選びの参考にしてほしい。
