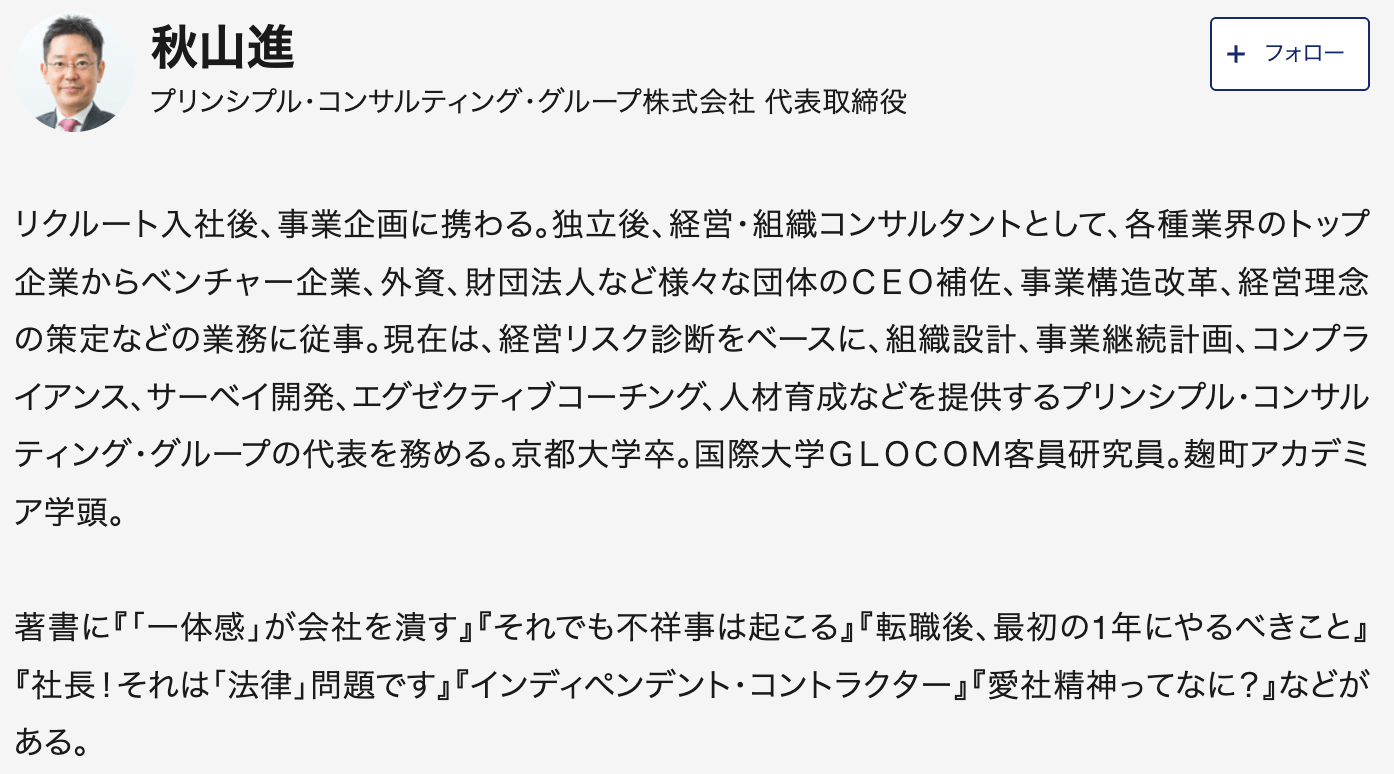もちろん、この実現のためには、自動運転などの技術発展、既存の関連業界との調整、法体制の整備など、あらゆる対応が必要となるが、現在、エストニアなどで進められている取り組みの結果によっては、実現可能性が高まってくる。
大変化にどう備える?転職のヒントにして乗り切ろう
これらの大変化に会社や個人はどう備えればよいのだろうか。言うまでもないが、AIやロボティクスの世界で重要なのはデータである。また、データ経済は「持てる者がますます富む」世界でもある。先行者がデータを独占し、データがあるから良いサービスが生まれ、そうであるがゆえに後発はなかなか追いつけない。
これは企業だけでなく個人にも当てはまる。
学生の一部はすでに生成AIを学習パートナーとして使い、学び方そのものを自動化している。一部の企業人はこれまで時間をかけていた作業をAIに代替してもらい、より重要で判断力のいる仕事にシフトしている。これらを早く試した人と拒否した人の間に、将来埋めがたい格差が生まれるであろうことは想像に難くない。
ただ、これらの変化がどう影響しあい、どのような未来になるかはまだ不透明である。
だからこそ、複数の試みを同時に走らせ、いろいろな経験を積むべきだ。企業も一つの領域や方法に賭けるのではなく、小規模な実証実験を多数並行する方がリスクヘッジできる。
もしかしたら、あなたの会社の役員は、眉間にしわを寄せ、「変化の時代には軽々に動いてはならぬ。他社の先行事例をしっかりと見て慎重に判断すべし」などと、それらしく語るかもしれない。役員連中がその調子であれば、もう見切ったほうがいい。未来をつかみたいなら、早めにそんな旧態依然とした組織からは脱走すべきだ。
何が悲しくて大会社で「パワポ芸人」をやり続ける必要があるのか。AIやロボティクスを積極的に使う変化のあふれる職場、少なくとも自社データをバリバリ使って生成AIを自由自在に使用できる環境のある職場に何が何でも転職することを強くすすめる。まだギリギリ間に合うはずだ。