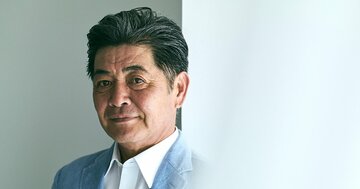そういった故障しがちな選手に対しては、トラックマン(編集部注/動作解析に用いる測定器。球速、回転数、回転軸、スライダーのような横変化量、フォークのような縦変化量などを測る)などで動き方のチェックをしつつ、メカニックな部分での検証もするようにしていました。
ピッチャーの場合はまず、フォームのバランス、連動性をチェックします。
さらに筋力なども細かくチェックしていき、そこで問題箇所が見つかればコーチやトレーナーと話し合いながら、改善メニューを考えていきます。
フィジカル的には何の問題もないのに、故障しがちというピッチャーも中にはいます。そういったピッチャーは、実はずっと以前(プロ入り前、あるいはチームに移籍してくる前)に大きな故障を抱えていたということが多く、それが再発したとなれば手術なども検討していかないといけません。
いずれにせよ、私たちはその選手の未来を考えたときに「何が一番最適、最善なのか」を常に考えるようにしていました。
ケガを防ぐ近道は
体力をつけること
プロのピッチャーの「投げるための体力」とは、単に100球、200球投げられるから「体力がある」ということにはなりません。先発ローテーションに入れば、5日から1週間に1回は必ず登板が求められます。それを1シーズン、続けられるだけの体力があるかどうか。プロの「投げるための体力」とはそのことを意味しています。
シーズンの後半にもなれば、疲労はピークに達します。それでも中5日、場合によっては中4日での登板を求められることだってあります(私が現役のときは中3日で投げろと言われたこともありました)。
そういった過酷な状況に置かれても、ベストなピッチングが続けられるのが一流のピッチャーといえます。それを3年、5年と続けられれば、そのピッチャーは「超一流」と呼ばれるようになるのです。
投げる体力のないピッチャーには、シーズンが終わると同時に「オフの間にこれをしておきなさい」という課題を出しました。