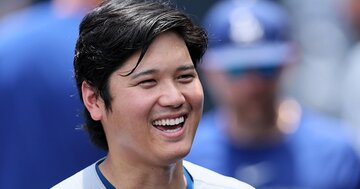ただ事実を言われただけと
思えば心を乱されずに済む
侮辱に敏感なのは現代人だけではない。古代ローマで侮辱と考えられていた例をルキウス・アンナエウス・セネカ(編集部注/ローマ帝国の政治家、哲学者、詩人。ストア派哲学者であるとともに、ラテン文学の白銀期に多くの著作を残した)の文章から引用してみよう。
「だれそれは今日、私の訪問を拒絶した。他の者たちは招きいれているのに」
「私が話しているとき、あいつは傲慢にも耳を傾けず、あからさまにせせら笑ったりした」
「私は上座を与えられず、下座に座らせられた」。
今日でも十分に侮辱として受け取られるものばかりだ。
侮辱されれば、人はたいてい怒る。怒りは心の平静を乱すネガティブな情動だから、ストイック(ストア哲学の信奉者)は侮辱されても怒らないですむ戦略をつくり出そうと考えた。いわば、侮辱の持つ針を取り除くための戦略である。
戦略のひとつは、侮辱されたときには少し立ち止まり、相手が言ったことが本当かどうか考えることである。本当ならば心を乱す理由はほとんどない。
たとえばだれかに禿げと言われてばかにされたとする。実際に禿げているのであれば、心を乱す理由はほとんどない。「なぜそれが侮辱なのか」とセネカは尋ねる。「分かりきったことを言われているだけなのに」。
尊敬できない人からの侮辱は
自分の正しさの証明
エピクテトス(編集部注/古代ギリシアの哲学者。奴隷の身でストア哲学を学び、解放され自由人となると、哲学の学校を開いた)が勧めているもうひとつの戦略は、侮辱されたときには立ち止まって、相手がどれほどこちらのことを知っているのかを考えるというものだ。
相手が私を悪し様に言うのは、別にこちらの感情を傷つけようとしてでなく、心底そう思っているからか、あるいは自分にはそう見えているよと知らせているだけかもしれない。
こういう相手には、その正直さに怒るよりもむしろ、落ち着いて彼をただすべきである。
とくに強力な戦略は、侮辱をしてきた相手について考えることである。
もし私が相手を尊敬し、その意見を大切にしているならば、その批判の言葉は私の心を乱すはずがない。