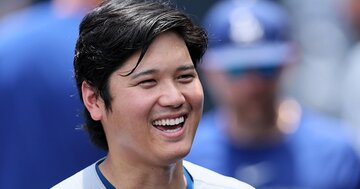セネカは、カトー(編集部注/マルクス・ポルキウス・カト・ウティケンシス。共和政ローマの政治家、哲学者。ストア哲学の研究を行ない、必要最小限の衣服で生活していた)がひどい侮辱を受けたときにユーモアで返したことをあげて、賞賛している。
カトーがある事件を弁論していたとき、敵対していたレントゥルスという名の男がカトーの顔につばを吐いた。怒りもせず、侮辱を返すこともせずに、カトーは顔にかかった唾を静かに拭き、それからこう言った。
「証人になってもいいがね、レントゥルス。人はあんたが口が使えないと言っているが、それは間違いだな!」。
セネカはまた、ソクラテスがこれよりひどい侮辱を受けたときの反応をあげて褒めている。
ある人がソクラテスに近づき、警告もなく耳に平手打ちをくらわせた。ソクラテスは怒りもせずに冗談で返した。いつ兜をかぶって外出したらいいのか分からないとは厄介なことだ、と。
突っ込まれたくないことは
自虐ネタにしてしまえばいい
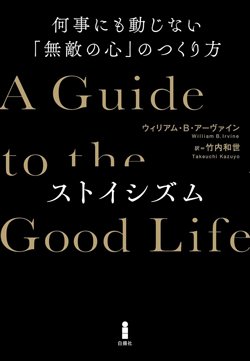 『ストイシズム:何事にも動じない「無敵の心」のつくり方』(ウィリアム・B・アーヴァイン著、竹内和世訳、白揚社)
『ストイシズム:何事にも動じない「無敵の心」のつくり方』(ウィリアム・B・アーヴァイン著、竹内和世訳、白揚社)
侮辱に対して使えるユーモアのうちで、自己卑下のユーモアはとくに効果的である。これについてもセネカが例をあげている。
ヴァティニウスという名のその人物は、首が腫れ物でおおわれ、足も病気でひどいことになっていたが、始終自分の惨めな状態について冗談を言っていたため、他の人たちはそれに付け加える言葉がなかった。
エピクテトスもまた、自己卑下のユーモアを使うことを勧めている。たとえば、だれかに悪口を言われた場合、むきになって対抗するのではなく、その侮辱の出来がよくないことを指摘するのである。たとえば、「本当に私のことをよく知っていたら、これだけの欠点ですむはずがない。私には他にもっとひどい欠点があるんだから」と答えればよい。
侮辱を笑い飛ばすことは、侮辱した人間もその侮辱そのものも、こちらがまじめに受け取っていないことをほのめかしている。これはむろん、侮辱した人間を間接的に侮辱することになる。相手はがっくりくるだろう。こうして侮辱にユーモアで応えるのは、侮辱を返すよりはるかに効果があるのだ。