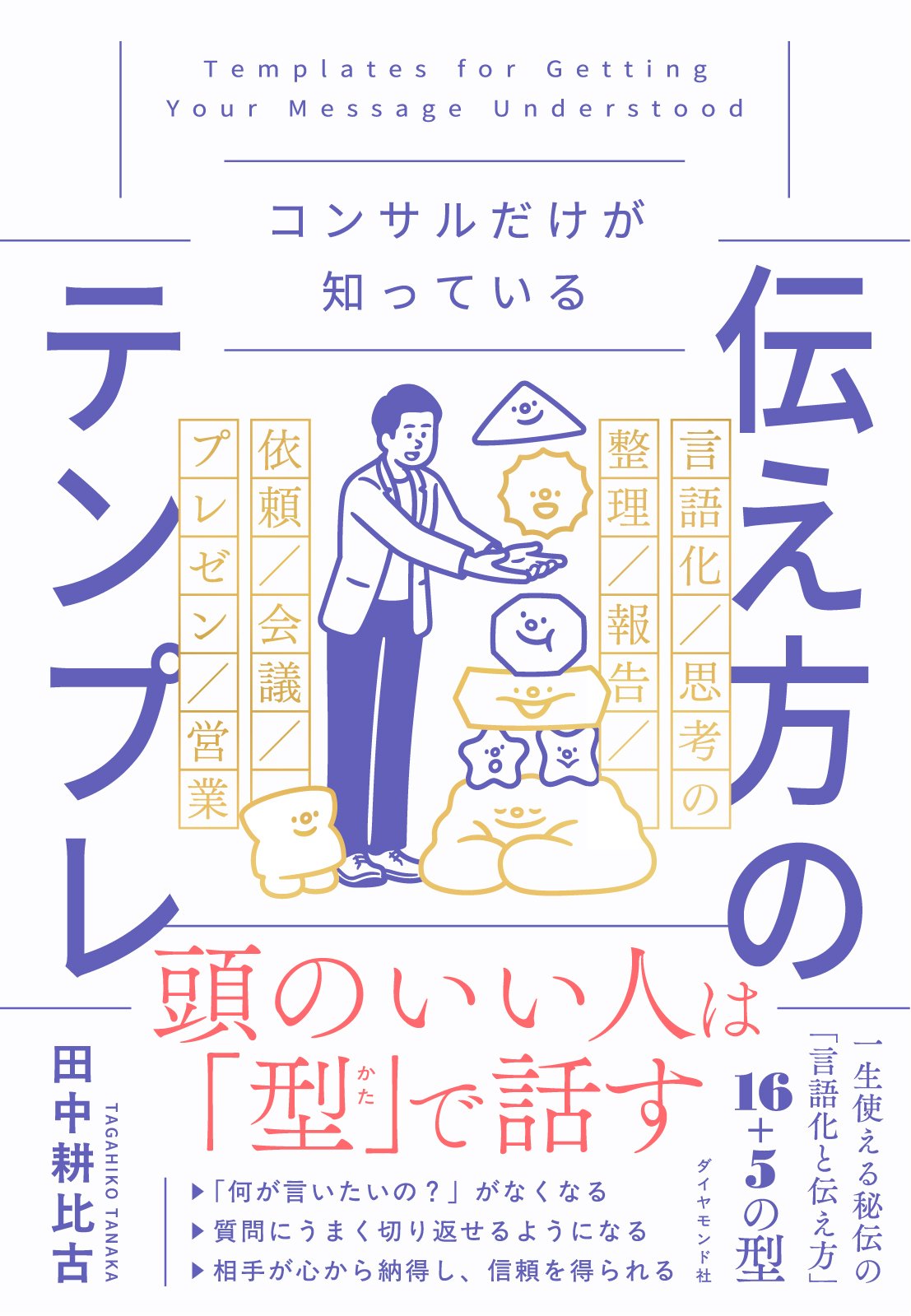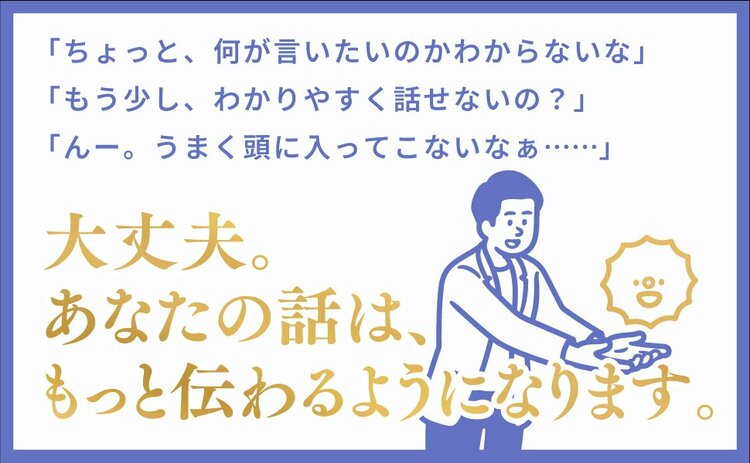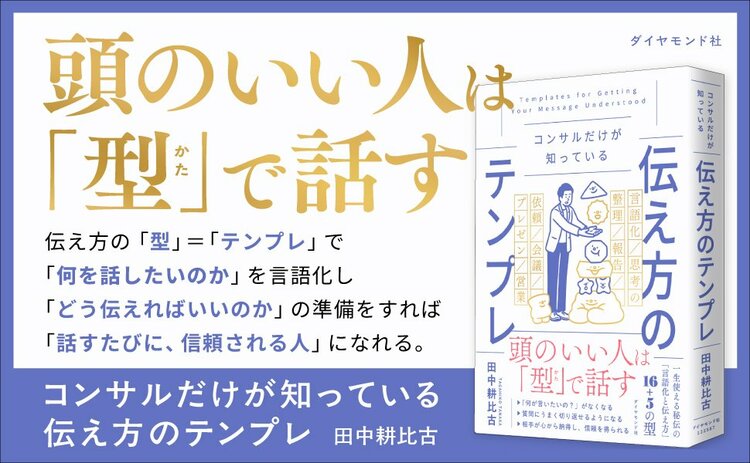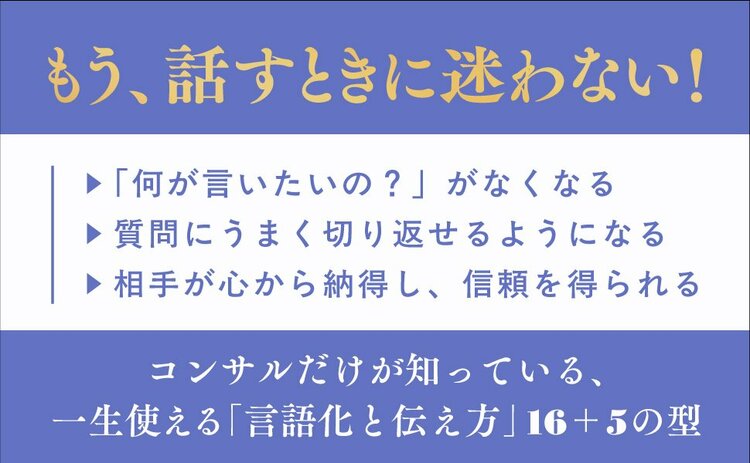「一生懸命に考えたのに、思ったように伝わらない」「焦りと不安から自分でも何を話しているかわからなくなってしまう」…。言っていることは同じなのに、伝え方ひとつで「なんでこんなに差がつくんだろう」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
コンサルタントとして活躍し、ベストセラー著者でもある田中耕比古氏の著書『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』から、優秀なコンサルが実践する「誰にでもできるコミュニケーション術」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「がんばって説明しなきゃ」と思い、話しすぎる
説明が下手な人にならないために必要なのは“がんばった気持ち”を手放す技術です。
褒めてほしい、よくがんばったねと労ってほしい、そういう気持ちを手放すと、話はシンプルで伝わりやすくなります。
「すべてを伝えようとしない」
これが、伝え方において、最も重要で、そして、最も忘れられがちなポイントです。
説明に慣れていない人ほど、
「考えたことは、すべて伝えきらなくちゃ」
「がんばって考えたので、その過程もしっかり理解してほしい」
そんな気持ちを持ちやすいものです。
しかし、聞き手の立場に立って考えてみるとどうでしょう。
・話が長くて、流れが読めない
・関係ない情報が、たくさん混じってくる
・要点がわからず、混乱する
こんな状態になってしまうと、こちらが話せば話すほど、相手は「聞くモード」ではなくなっていきます。
だからこそ、情報を「捨てる勇気」が必要なのです。
伝えたい気持ちを一度横に置いて、伝えるために「引き算」をする。
これが、「引き算テンプレ」です。
聞き手が受け取れるものだけに絞る「引き算テンプレ」
「引き算テンプレ」は、次の3ステップで進めます。
ステップ①:聞き手の立場に立って考える
ステップ②:相手にとって必要な情報だけを絞り込む
ステップ③:要点に集中して伝える
ステップ①:聞き手の立場に立って考える
本書の中で、なんども同じようなことを考えてきていますが、ここでも「ロールプレイテンプレ」の視点は特に有効だと思います。
「ロールプレイテンプレ」のステップ①~③、
ステップ①:聞き手の立場や背景を想定する
ステップ②:その相手の「知っていること」と「知らないこと」を分ける
ステップ③:相手が「気にしていること」、「興味のあること」を考える
がそのまま使えます。
相手が、何を知っていて、何を知らないのか。
どんな情報を知りたいのか、どんなことに興味があるのか。
まずはそうしたことを考えます。
ステップ②:情報の絞り込み
「ロールプレイテンプレ」のステップ④は、相手の興味に合わせて、情報を並べ替える、というお話でしたが、今回は引き算ですので、相手の興味関心から外れることは「思い切って捨てる」ことになります。
情報の取捨選択に際しては、「幹と枝葉テンプレ」で整理してきた内容が活きてきます。
大事なこと、伝えるべきこと「だけ」を決めます。
枝葉、つまり補足情報・参考情報は、いったん捨てます。そうした内容は「聞かれてから答える」という、「守備固めテンプレ+打ち返しテンプレ」のスタイルにしましょう。
具体的には、
・結論に至るまでの過程・プロセスは、バッサリ切る
・強調表現・修飾的な言い回しは、一度、すべて捨ててみる
・導入部を極限まで絞り込む
といったアプローチが効果的です。
結論に至るまでに、何をやったかというのは、時系列での考え方です。物事を考える際には有用ですが、伝える際には邪魔になります。思い切って捨てましょう。
また、「膨大な」「非常に」「極めて」「すばらしく」などの強調表現や、「たいへんな苦労を経て」「そこに大きな困難がありまして」「膨大な資料に基づいて」などの修飾的な言い回しは、話の筋とは直接関係しません。いったん、消してしまいましょう。
もし導入部が長くなる場合は、「必要のない前提情報を盛り込み過ぎている」というリスクがあります。相手が知っていることは、伝えない、もしくは、伝えるにしても、簡単な確認に留めるなどのテクニックを用いましょう。
「寄り添いテンプレ」で行ったように「背景情報・前提情報」を整理した上で、「ここから減らせるものはないか?」と確認していくのが良いと思います。
ステップ③:要点に集中する
そうして情報を整理したら、話の本筋だけに集中して伝えます。
もちろん、必要な背景情報・前提情報は伝えるべきですし、話術としてのアイスブレイクなども必要に応じて行うべきです。
しかし、本筋に入ったら、まずは、一本道で結論まで進んでいきましょう。
できるだけ、真っ直ぐ、迷いようがない道を進むのです。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の一部を抜粋・編集したものです)