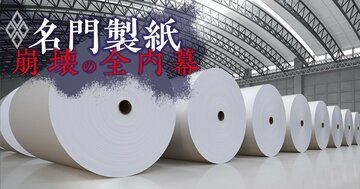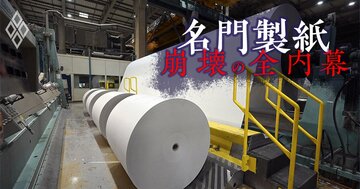Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
住友グループの名門ガラスメーカー、日本板硝子が苦境にある。約20年前の巨額買収の後遺症は今も続き、過剰債務、過小資本、低収益の三重苦にあえいでいる。同社は抜本的な構造改革である中核事業からの撤退を見送ったが、実は問題の根はさらに深い。新たに、巨額買収時の“不平等条約”によって現預金の大半が自由に使えないことが、ダイヤモンド編集部の取材で分かった。特集『名門ガラスの亀裂 巨額買収に潜む罠』の#2では、独自入手した内部資料や関係者への取材を基に、資金繰り悪化を招いている資金制約の中身を明らかにするほか、その「足かせ」が抜本改革を阻んでいる実態を解説する。(ダイヤモンド編集部編集委員 清水理裕)
日本板硝子の中核事業「撤退先送り」の真因
巨額買収時の“不平等条約”による「足かせ」
住友グループの名門ガラスメーカーである日本板硝子が、極秘検討していた不振の中核事業からの撤退を見送った――。
同社は2006年に約6000億円を投じた英ピルキントンの巨額買収で過大な有利子負債を抱え、過剰債務、過小資本、低収益の三重苦にあえいできた。中でも、連結売上高の半分を占めながら収益性が低い自動車用ガラス事業が、長年の経営課題となってきた。そのため同社は25年3月期中から、同事業からの撤退を水面下で検討してきた。
ところが、この夏、撤退判断そのものを27年3月期以降へ大幅に延期する決定を下した。判断先送りの要因の一つには、同社が想定していた、自動車用ガラス事業の売却額と現実との大きな乖離があった(詳細は本特集#1『【独自】日本板硝子、低収益な中核事業からの「撤退先送り」が判明!背景に甘い売却計画や債務超過リスク…20年前の巨額買収が大リストラの障害に』参照)。
実は、もう一つ抜本策の決断を妨げる要因があった。それが、約20年前に売り上げ規模が約2倍のピルキントンを買収したときの “不平等条約”である。ダイヤモンド編集部の取材で、グループ内の現預金の大半を自由に動かせない制約が存在することが判明した。
日本板硝子の見かけ上の現預金は25年3月末で653億円だ。だが、この制約により、日本板硝子の資金繰りはバランスシート上の見掛け以上に苦しくなっている。同社のメインバンクは三井住友銀行で、三井住友信託銀行、みずほ銀行、日本政策投資銀行を加えた計4行が主要取引行だ。
25年3月末で5248億円の有利子負債を抱える日本板硝子は、主要取引行以外からも資金を借りている。三菱UFJ銀行、りそな銀行、SBI新生銀行、あおぞら銀行といった都市銀行や大手行はもとより、農林中央金庫に加え、三十三銀行(三重県)や静岡銀行、西日本シティ銀行(福岡県)といった地方銀行からも融資を受けている。
さらに近年は、静岡中央銀行などの第二地銀や農業協同組合(JA)にまで資金の調達先を広げている。実はこの状況を産んだのも「足かせ」に理由がある。2006年の巨額買収の際に、まるで罠のように仕込まれたスキームが20年後の日本板硝子を苦しめているといえる。財務諸表からだけでは読み解けない、この「足かせ」の実態を、次ページで詳報する。