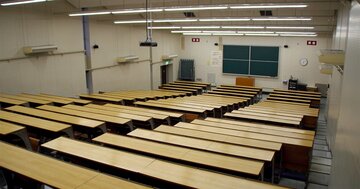古村典洋(注4)は、厚生労働省の21世紀成年者縦断調査の2002年から2015年までの個票データを用いて、出産を経験した女性が、出産を経験しない女性に比べて、どの程度所得が低下するか計測を行っている。
それによると、出産の前年と比較して、出産の翌年の所得は6割以上低く、その後も差はほとんど狭まらない。
2000年代は概ね約半数の女性が出産を機に退職していたので、就業を続けた人も出産後職場復帰しても平均して所得が3割程度低い水準にとどまったことを示唆する。古村の試算によると、男女賃金格差のうち約半分がチャイルドペナルティによるものだという。
長時間バリバリ働く男性と
深夜労働が難しい女性
一般に、男性は長時間労働をしやすく、女性は家庭での責任が重かったり深夜労働によるホルモンバランスの乱れが大きかったりといった理由などから、長時間労働をしづらい傾向にある。
したがって、職位や等級が上がるにつれ、女性の昇進昇格率が下がる場合は、責任が重くなるにつれ労働時間が増えているからではないか、あるいは結婚・出産などのライフイベントに合わせて働き方を調整できる柔軟性がないからではないか、といった疑問を持って、職位別の労働時間、昇進率、離職率などの数字を見比べる必要がある。
性別職域分離(編集部注/職業や職務内容が男女で偏っている状態)には、職域によって平均労働時間や柔軟な働き方の可否が異なることが影響を与えていることが多い。
それを確認する簡単な方法の1つが、労働時間が長い職域(または部門)と労働時間が短い職域(部門)で、男性と女性の平均労働時間と平均昇進率の差を比べてみることだ。
労働時間の長い職場ほど、労働時間の男女差も昇進率の男女差も大きければ、長時間労働が男女格差をもたらしている傍証となる。
注4 古村典洋(2022)「仕事・働き方・賃金に関する研究会―一人ひとりが能力を発揮できる社会の実現に向けて」報告書、第3章「チャイルドペナルティとジェンダーギャップ」財務総合政策研究所.
https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2021/shigoto_report.html
https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2021/shigoto_report.html