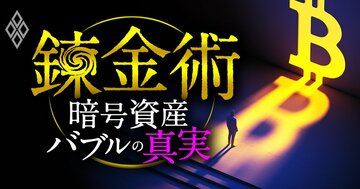「面白い人が集まるテレビ局にしたい。『コンテンツなんて誰でも作れる』とも言われる時代に、なぜ日本テレビを選ぶのか。それは、経験豊富なクリエイターが自分の判断軸を公開し、擬似的にでも日々コミュニケーションが取れて、自分の成長につながる環境があるから。そして、現場のトップ自身が『自分はAIより面白くなきゃいけない』と本気で向き合っているから。そんな環境が作りたいと、八重沢さんの姿を見ていて思いました」
 八重沢さんの姿勢を通じて、また新たな目標を見つけた辻さん Photo by M.S.
八重沢さんの姿勢を通じて、また新たな目標を見つけた辻さん Photo by M.S.
「AIが人をもっと情熱的にするし、あったかくするし、面白くする」と辻さん。八重沢さんも「僕はAIを育てようと思っていたんだけど、辻さんの『AIが人を育てる』という視点も面白い。パワーワードだ」と笑う。
一方で、情熱があっても全ての番組でAIエージェントが有効とは限らない。「バラエティ番組はどうだろう。笑いって難しいですよね」と八重沢さん。「バラエティは、『誰を呼び、どういう時勢で、何を言ってもらうか』という複雑な変数が絡む。今は見当がつきません。また企画会議に潜入するしかない」(辻さん)
思いのあるコンテンツだけが生き残る
まだ道半ばだが、辻さんは、「AIの社会実装に実直に向き合ったプロジェクトだった」と振り返る。
「AIを使ってできるところまでやってみたという検証は、実際の現場で使うには打ち上げ花火のようで永続性がない。日々の業務に本気で使おうとしたとき、私はやっぱり人の力を信じていたいし、人が気持ち良く使える環境を整えて、人の可能性をもっと引き上げることを一番大事にしたいです。今回のプロジェクトを通して、やはりAIは手段であり、人が主役だと再認識できた。これは大きな成果です」
八重沢さんいわく、長く愛される番組には共通点があるという。
「打算的なコンテンツって、あまり長く続かないんですよね。生き残るのは、制作者の思いが強いコンテンツです。制作者の熱い思いに演者も共感し、一緒になって番組をつくり上げている。今後はより、思い重視になっていくと思います。なっていくといいな」
結局、人を動かすのは人だ。AIがいかに優秀になろうとも、それが覆ることはきっとない。ただ、AIが人の個性や創造性を引き出し、育てていく。そんなちょっと逆説的な未来が静かに始まっていた。