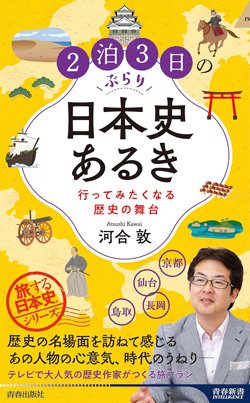このように、政宗に天下取りの野望があったかどうかはわからないが、少なくとも時の天下人からはそのふるまいが傲岸不遜に見え、脅威を抱かせる存在に思えたのだろう。
さて、慶長遣欧使節である。支倉常長らはメキシコを経てヨーロッパに上陸、スペインやローマを回るが、結局は冷たい対応をされてメキシコとの交易は認められなかった。すでに幕府は全国に禁教令を出しており、スペインはその情報を知っていたのだ。
カトリック国のスペインは布教と交易を一体と考えており、当然、政宗の真意を疑い、交易の希望を拒んだのである。
常長は出立から7年後の元和6年に帰国したが、政宗は領内でのキリスト教を厳禁してしまい、常長も冷遇されて2年後に57歳で死去した。さらにその後、支倉家の家臣にキリシタンがいることが発覚すると、常長の嫡男である常頼は責任を負わされ、処刑されてしまった。なんとも哀れな末路である。
慶長遣欧使節は失敗に終わり、交易による領内の復興はかなわなかった。しかし政宗は津波被害にあった沿岸地域を塩田にしたり、港の拡大や河川の改修を積極的に進めたりした。そして膨大な新田を開発し、とれた米を石巻などの港から大消費地である江戸に送るようになった。
この江戸廻米は、年々増えて江戸で消費される米の10パーセントにも及ぶようになり、仙台藩に莫大な富をもたらすことになった。