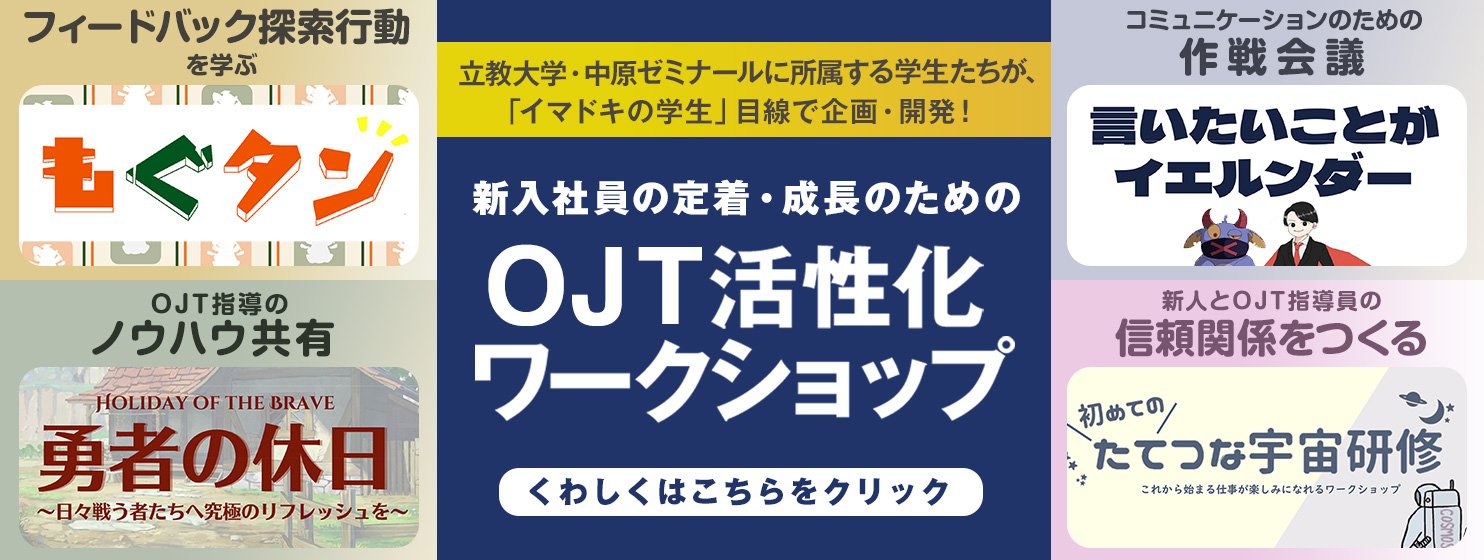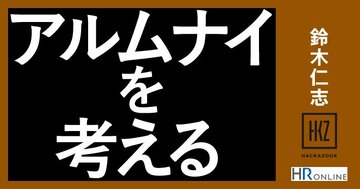面接力の高い企業の“ハイブリッド面接”方法は…
本稿の最後に、オンラインと対面をうまく使い分けながら「効率的かつ効果的な面接」を実施している企業の事例をお伝えします。
この企業では、1次面接はオンラインで実施をしており、採用担当者と部門のエンジニア面接官が対応しています。最終面接は対面で実施をし、部門の事業部長と人事部の責任者が面接を行っています。
まず、1次面接ではオンラインで技術力を見極める面接をします。人事と部門側ではっきりと役割を分けており、人事は会社説明や条件面のヒアリングに徹します。部門のエンジニア面接官は技術ジャッジに集中します。ライブコーディングテストの後に、技術テーマを設定して候補者とディスカッションをします。事前に「技術面接」である旨を伝えているため、違和感のない面接の場がセットされており、スムーズに進行します。面接合否についても、技術力の高低をどう判断したかを伝えているため、候補者にとって良い体験になっています。
最終面接では、人柄や価値観を確認します。表情、視線、身振り手振り、声のトーンなど、言葉以外の情報を得ることができますので、企業と候補者双方で、人柄や考え方、カルチャーを判断することで入社後のミスマッチを防ぎます。面接の後に社内案内もしており、働く人々の雰囲気や職場環境を伝えるようにしています。オンラインと対面の性質をうまく利用している点が素晴らしいです。
働き方の多様化と非言語コミュニケーションの価値
近年、出社回帰の動きが加速するなか、エンジニアの働き方にも大きな影響が出ています。転職を考える候補者からは「リモートワークやハイブリッドワークを希望する」という声が非常に多く聞かれます。パンデミック以前の「フル出社」が当たり前だった時代が、いまでは遠い過去のように感じられます。新型コロナウイルスは、私たち一人ひとりの働き方に対する価値観を根本から変えました。場所や時間に縛られない働き方が、生産性やワークライフバランスの向上につながるという認識が広く浸透しました。しかし、リモートワークが普及した一方で、「非言語コミュニケーション」の価値が改めて見直されています。オンラインでのやりとりでは、些細な表情や声のトーン、場の空気といった言葉にならない情報が伝わりにくくなりがちです。
こうした背景を踏まえ、採用活動においても工夫が必要です。もし、自社の採用改善を検討されているのであれば、「オンライン」と「対面」を組み合わせたハイブリッド面接の導入をぜひご検討ください。面接力の高い企業事例でもご紹介しましたが、一次面接は候補者の負担を考慮してオンラインで行い、最終面接は対面で実施することで、お互いの人柄や雰囲気を深く理解する機会を設けることができます。ハイブリッド面接は、入社後のミスマッチを防ぐための効果的な手段になるはずです。