超音波による微小循環改善効果で
認知症を治す方法とは
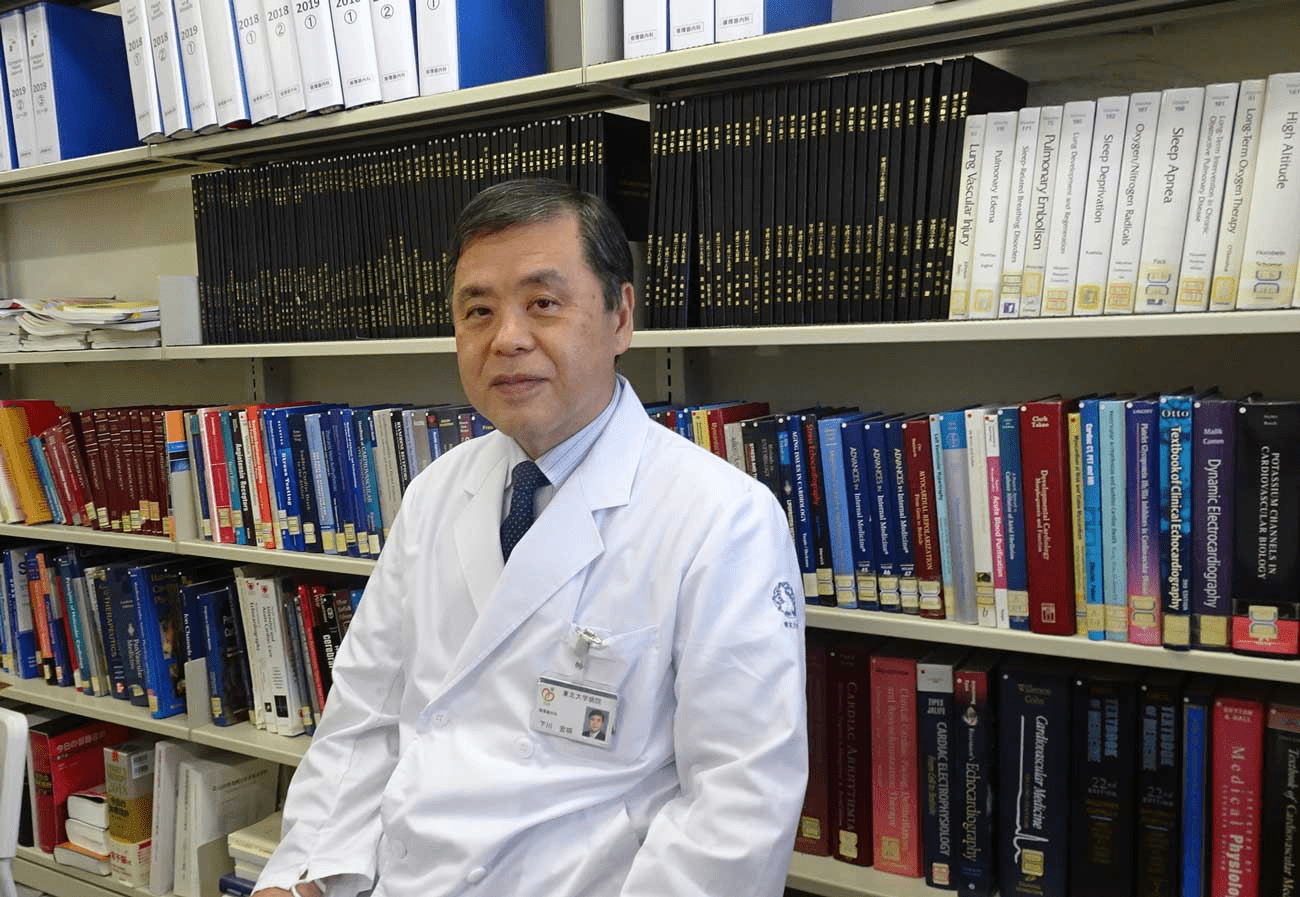 東北大学名誉教授・国際医療福祉大学特任教授の下川宏明氏
東北大学名誉教授・国際医療福祉大学特任教授の下川宏明氏
認知症は発症すると生活が著しく不自由なものになることなどから、日本人にとって「最もなりたくない病気」だと言われている。もしも、アミロイドβ仮説とは別のところにアルツハイマー病の原因があるとしたら、それはいったい何なのだろうか。
実は、アミロイドβ仮説とは違う方向からの研究・開発も進んでいる。最注目の研究は2027年にも実用化されそうな状況だ。
その研究とは、超音波による認知症治療だ。
取り組んでいるのは東北大学名誉教授・国際医療福祉大学特任教授の下川宏明氏。もともとは循環器内科医で、2010年に開発した低出力体外衝撃波による狭心症治療装置は先進医療として承認され、これまで世界25ヵ国で1万人以上の患者を救ってきた。
現在は、低出力衝撃波を低出力パルス波超音波(※)に変えて、「微小循環障害の改善によって認知症を治療」することを目指している。健康診断で使われる心エコーや腹部エコー検査と同程度の出力範囲の超音波を照射するため、低侵襲性で安全に対する懸念も格段に軽減されるという。作用機序として、低出力パルス波超音波が有する、血管を新生させ、血の巡りが悪くなって障害された組織の機能を改善させる作用を利用するのである。
下川氏が認知症の研究を始めたきっかけは、アルツハイマー病と心筋梗塞などの動脈硬化性疾患は危険因子や予防法が共通していると気づいたことだった。そこから、「認知症は脳の微小血管の循環障害(微小循環障害)に起因する血管病である」との考えに基づき、研究開発を進めてきた。微小循環とは、末梢にある微小な毛細血管の血の巡りのことを指す。
「循環系で最も本質的な役割を果たしているのが微小循環です。心臓や太い血管も、微小循環系に適切に血液を供給するための補助装置とも考えられます。微小循環は、全身の細胞機能を規定していますので、虚血性心疾患も認知症も、結局は『循環不全病』なのです」(下川氏)
そもそも下川氏は以前から、アミロイドβ仮説に疑問を持っていたという。
「アミロイドβやタウ蛋白(アミロイドβと並ぶ原因物質と考えられている)といった物質だけをどんなに一生懸命減らしても、そうした開発治験の多くは十分な成果が見られません。アミロイドβやタウ蛋白の蓄積は、原因の一部かもしれませんが、あくまで海面に出た氷山の一角であって、海面の下には微小循環障害があるからです。







