実は胎児の時点で、脳は外部のさまざまな状況を知覚していることも分かっているので、脳を発達させる拘束条件は、生まれる前からあると考えていいでしょう。
他者との関わりが
自分という意識をつくる
これらはすべて、いうなれば「他者」です。置かれている環境や周囲の人たちはもちろんのこと、脳の容れものである頭蓋骨、さらには先人から受け継いできた遺伝子もまた、発現という拘束条件を与えるという意味では他者と言える。
私たちの脳は、つまるところ、そういう他者が与える拘束条件によって機能分化してきたのです。
私は、こうした他者との相互作用をモニターしている「もうひとつの自己」があると考えています。他者と直に関わる自己と、それを観測しているメタな自己意識。
両者が融合して初めてひとつの個体の中にひとつの自分というものができる。
このプロセスは、シナプスの刈り込み(編集部注/たくさんシナプスをつくっておいてから、周囲との相互作用において必要なものだけを残していくこと)が起こる生後数カ月から始まります。
ここでようやく自分という意識が生まれ、それをもって自分の肉体が真に自分のものになる、といったらいいでしょうか。
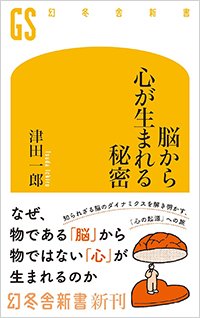 『脳から心が生まれる秘密』(津田一郎、幻冬舎)
『脳から心が生まれる秘密』(津田一郎、幻冬舎)
たとえば「自分の手」「自分の足」という意識で指令を下して「手を動かす」「足を動かす」ということができるようになる。他者からの拘束条件の下で変分的に機能分化した脳を、自らの意志で機能させられるようになるわけです。
脳はいかにして機能的になるのか。なぜ生命が、そもそも拘束条件の下で発達したり進化したりすることを選んできたのかは分かりません。
ただ、少なくとも拘束条件をかけている他者の存在によって、どうやら変分的に脳の機能分化、および分化した機能を自ら組織して機能させる「自己組織」が起こっているらしいことが分かってきました。
その意味で、私は通常の生物学的な自己組織(注2)と分けて、脳の自己組織を「拘束条件付き自己組織」と呼ぶことにしました。
いわばこれが、自転車の設計図に当たる「脳の設計図」なのです。







