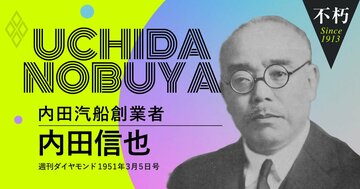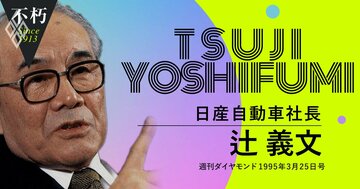1951年、日本がサンフランシスコ講和条約を目前に控え、占領から独立へと向かう節目に当たって、国際決済銀行副会長などを務めた銀行家で国際人でもあった加納久朗(1886年8月1日~1963年2月21日)が「ダイヤモンド」1951年3月臨時増刊に寄稿している。戦前・戦中・戦後を通して「世界から見た日本の位置」を冷静に見つめ直し、敗戦で富を失った日本が再び世界の一員となるための「精神の再建」を説くものである。
冒頭で加納は、日本を「世界の田舎者」と断じている。地理的な孤立だけでなく、国際知識の欠如と閉鎖的な精神構造が、戦争の惨禍を招いたと批判する。戦中の軍国主義と官僚主義がもたらした「独り善がり」を改め、国際社会の中で謙虚に学ぶ姿勢を持てと促す。そのための第一歩が「心構え」の転換である。
加納の提言の中心は「国際理解の深化」と「文化の成熟」にある。単に大人を留学させるのではなく、津田梅子らの例に倣い、若い世代を海外に送り出し、異文化の中で人格と教養を磨かせるべきだと述べる。日本人が米国の宗教的背景や富の使い方を理解できないのは、物質的貧困以上に精神的な「狭さ」に起因するとし、長期的な交流と現地体験によってしか真の理解は得られないと説き、短期的な経済発展ではなく、30年、50年先の真の平和の基礎を築くためにも、文化外交が不可欠だと語る。
また、加納は「日本文化の再定義」を求めている。伝統を誇るだけではなく、科学・思想・芸術の各分野で世界に貢献できる普遍性を持たねばならない。長唄や将棋が世界一でも通用しない、世界のどこでも尊敬される文化力を身に付けよと訴える。これは敗戦国としての卑屈さでも、かつての帝国主義的自尊心でもなく、「成熟した教養国家」としての再生を目指すべしという立場だ。
その根底にあるのは、「日本の富の再建は文化と教養に立脚すべきだ」という信念である。単に工業製品を効率的に作るだけでは国は豊かにならない。デザインや感性、美意識といった“文化の厚み”が商品の価値を決めるのだと説き、輸出産業すらも文化力に支えられるべきだとする。この思想は、後に日本住宅公団総裁として生活文化の刷新を進めた加納の実践にも通じる。
最後に加納は「日本人は日本を発見せよ」と結ぶ。つまり、日本人自身が自国の文化の可能性と限界を見極め、世界の中でどう生きるかを自覚せよという呼び掛けであった。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
冒頭で加納は、日本を「世界の田舎者」と断じている。地理的な孤立だけでなく、国際知識の欠如と閉鎖的な精神構造が、戦争の惨禍を招いたと批判する。戦中の軍国主義と官僚主義がもたらした「独り善がり」を改め、国際社会の中で謙虚に学ぶ姿勢を持てと促す。そのための第一歩が「心構え」の転換である。
加納の提言の中心は「国際理解の深化」と「文化の成熟」にある。単に大人を留学させるのではなく、津田梅子らの例に倣い、若い世代を海外に送り出し、異文化の中で人格と教養を磨かせるべきだと述べる。日本人が米国の宗教的背景や富の使い方を理解できないのは、物質的貧困以上に精神的な「狭さ」に起因するとし、長期的な交流と現地体験によってしか真の理解は得られないと説き、短期的な経済発展ではなく、30年、50年先の真の平和の基礎を築くためにも、文化外交が不可欠だと語る。
また、加納は「日本文化の再定義」を求めている。伝統を誇るだけではなく、科学・思想・芸術の各分野で世界に貢献できる普遍性を持たねばならない。長唄や将棋が世界一でも通用しない、世界のどこでも尊敬される文化力を身に付けよと訴える。これは敗戦国としての卑屈さでも、かつての帝国主義的自尊心でもなく、「成熟した教養国家」としての再生を目指すべしという立場だ。
その根底にあるのは、「日本の富の再建は文化と教養に立脚すべきだ」という信念である。単に工業製品を効率的に作るだけでは国は豊かにならない。デザインや感性、美意識といった“文化の厚み”が商品の価値を決めるのだと説き、輸出産業すらも文化力に支えられるべきだとする。この思想は、後に日本住宅公団総裁として生活文化の刷新を進めた加納の実践にも通じる。
最後に加納は「日本人は日本を発見せよ」と結ぶ。つまり、日本人自身が自国の文化の可能性と限界を見極め、世界の中でどう生きるかを自覚せよという呼び掛けであった。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
いよいよ国際仲間に入れるが
日本は「世界の田舎者」
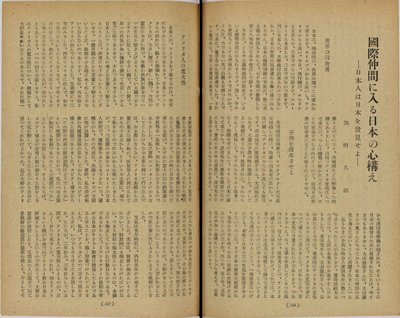 1951年3月臨時増刊より
1951年3月臨時増刊より
日本は、地理的に、世界の隅っこに置かれております。ヨーロッパからも遠いし、米国からも遠い。今日、飛行機がロンドンと東京とを、3日でつないでいます。 ニューヨークと東京とを、2日でつないでいます。
しかし日本人が大勢旅行できるわけではないから、日本が世界の田舎者たることに違いはありません。日本の国際知識の不足が、第2次大戦の仲間入りをして、70年間の蓄積した富を8割失って今や貧乏しております。