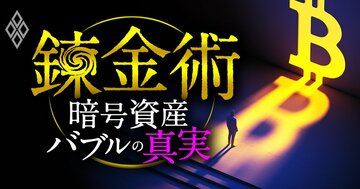現在の日本では、名目賃金の引き上げが売上価格への転嫁によって行われているために、物価が上昇し実質賃金が上昇しないのだ。
転嫁をよしとする経済政策には、基本的に大きな問題があり、それを根本的に変更する必要がある。
この点については、政治的にどのような立場を取るにせよ、答えは同じだ。つまり、どのような内閣が成立するにせよ、生産性向上のための政策が展開されなければならない。
ところが、昨年の参院選でも、先般の自民党総裁選でも、生産性向上に言及した政党や候補者もいたことはいたが、実現する具体的な政策については投資減税などの一般的なものにとどまり、深い議論はされなかった。
つまり、日本経済にとって最も重要な課題がなおざりにされている。
提案されたのは、減税や社会保険料引き下げによって税引き後所得を増やす政策だ。だが、こうした政策では、物価上昇の痛みを一時的に緩和することはあっても、経済全体の実質所得を増やすことはできない。
自民と維新の合意文書では、自公政権が掲げていた現金給付は行わないと明記されたが、何をするかといえば、ガソリン減税や電気・ガス料金の補助で、結局は従来の政策発想にとどまっている。
「デジタル敗戦」からの脱却
高度人材供給に大学改革は喫緊の課題
高齢化社会における日本の産業構造と貿易構造をどのようなものとして構想するかは、政治的立場によって意見が異なるだろう。
ただし、どのようなものを目指すにしても、生産性向上のための施策として、デジタル分野での発展を図ることが重要であることに違いはない。
デジタル敗戦が日本停滞の基本的な要因であることは広く認識されており、これまでもさまざまな内閣が施策を提案してきた。しかし、事態はほとんど変わっていない。
デジタル敗戦の背景には、高度人材の不足がある。それは日本の教育、特に大学での教育研究体制が、古い時代のものから脱却できずにいるからだ。このため、デジタル分野での新分野や事業を開発する産業界への人材供給が少なかったり、行政のデジタル化が遅れたりすることになっている。
自民・維新の合意文書では、「科学技術創造立国」実現のため科学研究費の大幅拡充が掲げられているが、具体的なものはなくお題目にとどまっている。
この問題を解決するためには、まず、日本の大学の構造を抜本的に改革することが必要だ。そして産業界や行政など、周辺領域のデジタル化との連動・接続を図ることだ。
これは、極めて難しい課題だが、決して解決不可能であるわけではない。
こうした日本が直面する主要な課題について、どの政党も明確な方向性を打ち出せていない。新政権誕生に至るこの10日余りを見ても、結局、合従連衡に全精力が消費されており、政策論議は表面的なものにとどまった。
政権構造の変革は、政治家のためにするものではない。それを国民のためのものとすることが必要だ。いま求められるのは、合従連衡ではなく、未来を設計する政治だ。
(一橋大学名誉教授 野口悠紀雄)