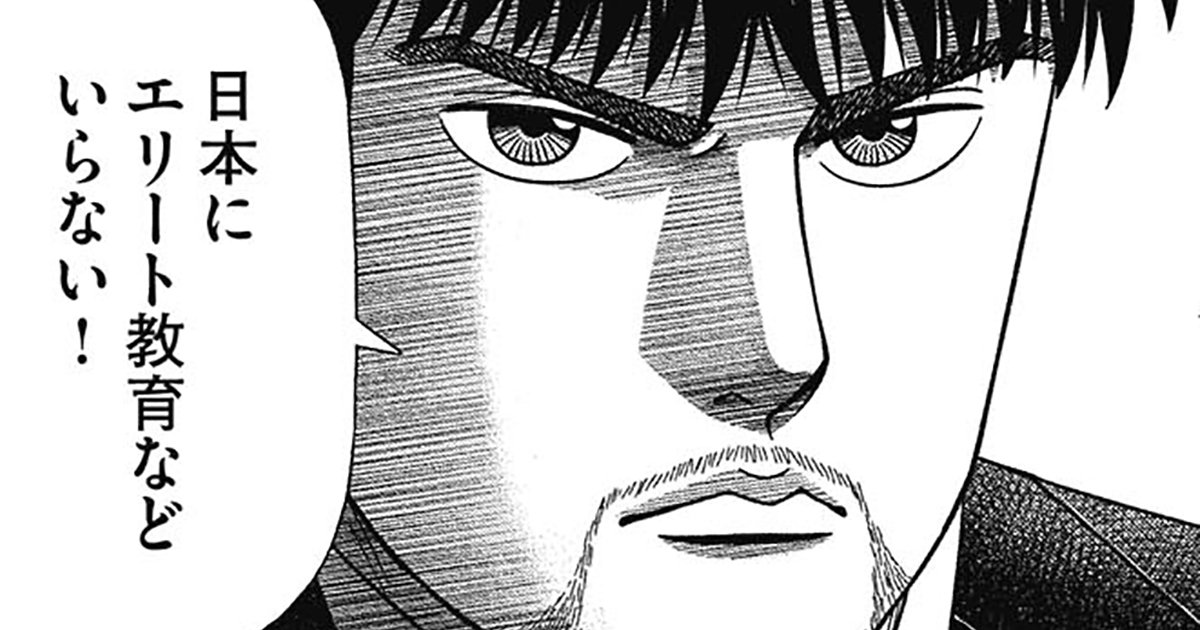 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第96回は、「エリート教育」について考える。
「まぁ、でも理解できないのはしょうがないよね」
東大合格請負人・桜木建二が理事を務める龍山高校では、学校改革に向けた理事会が開かれていた。欧米のエリート教育を目指す理事長代行の龍野久美子に対して、桜木は「日本にエリート教育などいらない!」と切り捨てた。
今の日本はエリート教育だろうか。受験は門戸こそ開放されているが、特に上位校では事実上のエリート教育になっている点は否めない。
傾向と対策が合否を分ける受験において、合格するためには専門の訓練が必要だし、その訓練には当然お金がかかる。そのようなお金を出せる家庭は、すでにそのような訓練を通して「エリート」になった人たちで構成されている。雑な単純化だが、ある程度真理であることは間違いないだろう。
もちろん「塾なし」合格も一定数いることは事実だ。だが「塾なし合格」という言葉があること自体がむしろ、その例外性を際立たせている。
私自身も私立中高や東京大学に通う中で、無意識に自らを上とみなした、生徒や学生の言動を目にしてきた。それは、単に自分たちの所属する集団以外の人たち、あえて言うならば「非エリート」を感情的にあざけり、バカにするという単純なものではない。
むしろ自分の育った環境が恵まれていることを十分に理解した上で、「自分たちが関わることはお互いにとってよくない」と距離をとろうとしているように思える。
「理知的に」「理路整然と」自分たちの優位性を主張し、「まぁ、でも理解できないのはしょうがないよね」といったふうに諦観したような態度をとる。これらの主張は、相手に言うのではなく、自分たちと同じ「エリート」同士が集まる時に行われることがほとんどだ。
上野千鶴子が語った「環境のおかげ」
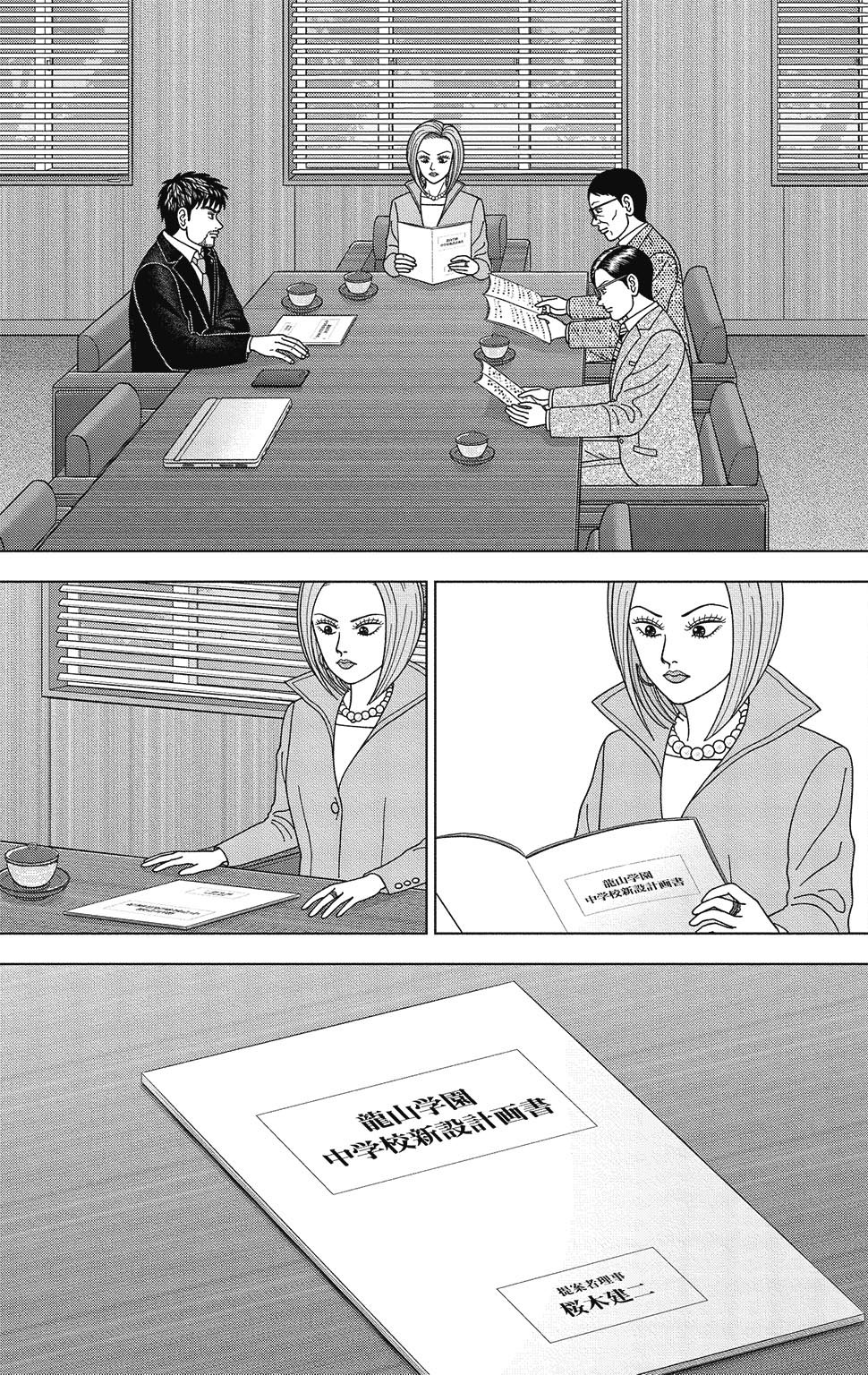 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
いわゆる中堅大学と呼ばれるところに進学した中高時代の友人から「高校の時よりもレベルが低すぎて、友人たちの言動を全く面白いと思えない。だけど、そこに優越感を覚えている自分に嫌気がさす」というようなことを聞いたことがある。
他にも、無意識に経済的に困窮している環境を観察対象として見ているような節も伺える。人生経験として肉体労働のバイトをしてみたい、といった願望は、それを生業にしている人からすればとても残酷な言葉かもしれない。
でもそんなことに思いをはせる自分に「お前は何様なんだ」と言いたくなる。
経済的に恵まれた生徒たちが「かわいそうだと思ったから」といって、貧困家庭の子どもたちの支援活動を無償で行う構図。それに対して、「偽善だ」という意見と「何もやらないよりはよっぽどいい」という意見が集まる。
どこまで行っても割り切れないし、誰にとってもモヤモヤは残る。あるいは、私のようにそのモヤモヤを抱くこと自体に自己嫌悪を感じるようになる。この思考のループから逃げたくて、結局は自分たちと近い集団に混ざろうとする。
その言動が何かと話題を呼ぶ上野千鶴子・東京大学名誉教授だが、2019年度東京大学入学式の祝辞でこのような強烈なメッセージを残している。
「『がんばったら報われる』とあなたがたが思えることそのものが、あなたがたの努力の成果ではなく、環境のおかげだったこと忘れないようにしてください」。
自分の環境に傲慢(ごうまん)になってはならないし、自分の努力を卑下する必要もないし、自分と違う環境の他者を哀れんだりするのはよくない。その間で揺れ動く、いつまでたっても消えないモヤモヤから逃げないことが大切なのではないだろうか。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







