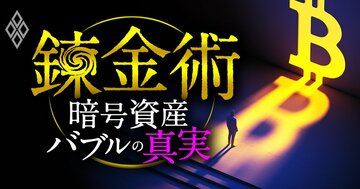ただ、本当にこれを実行に移した場合、凄まじい「痛み」が伴う。それに日本人がどこまで耐えられるかがポイントだろう。
まず、外国人労働者、つまりは低賃金労働者を雇うことでしか会社を存続できない零細中小企業が大量に廃業・吸収合併に追い込まれる。「いや、そこはロボットやAIの出番だろ」ということを言う人もいるが、低賃金労働者に頼らざるを得ないような事業者は、そのような設備投資ができないから「労力の輸入」に頼っているのだ。
日本の企業の99.7%は中小企業で、日本人の7割がそこで働いている。そこで「中小企業」という響きから「下町ロケット」の佃製作所のようなところをイメージするだろうが、それは少数派だ。実際の「中小企業」の6割は、社員が数名という家族経営の小規模事業者であり、ほとんどはサービス業だ。
つまり、「外国人労働者がいなくてもAIやロボットでどうにかなる」というのは、絵に描いた餅どころか、日本の産業構造とかけ離れた「妄想」に過ぎないのだ。
そうやって体力の弱い会社が大量に廃業・吸収合併されていくなかで、日本の「安くてうまい」「安くて高品質」もどんどん消えていく。
よく言われるように、外国人労働者への依存が高いのは建設現場、農業、介護だが、実は日本の「安くてうまい」の代名詞であるコンビニグルメなどは、外国人労働者がいなくては立ち行かない。
大手コンビニやスーパーから総菜製造の委託を受けている食品製造業など「中食」にかかわる企業の業界団体「日本惣菜協会」の資料によれば、全食品製造業の労働者約120万人のうち、半分近くが総菜製造に従事している。しかも、「多くの作業者は、外国人」だという。
この分野は採算が取れないのでロボット化も難しいと言われてきた。それでも外国人労働者の数を減らすために推進するというのならば当然、「価格転嫁」しなくてはいけない。つまり、これまで通りの「安くてうまいコンビニグルメ」は難しいということだ。