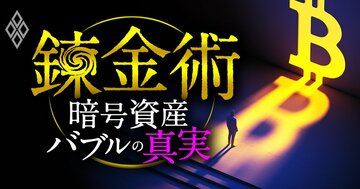実際、この「労力の輸入」によって炭鉱を運営する会社は大いに儲かったが、日本の労働者の待遇は一向に上がらなかった。程なくして小林多喜二の「蟹工船」に描かれたようなブラック労働が定着していったのである。
しかも、問題はそれだけではない。もともと「日本人が嫌がる仕事を外国人にやらせる」という発想なので当然、職場での扱いは非人道的になる。日本人労働者と露骨に格差をつけられる。「いじめ」もそうだが、加害者側というのは「あれ? そんなことあった?」と忘れてしまうが、被害者側の遺恨、復讐(ふくしゅう)心というものは何十年経過しても残る。
この「労力の輸入」以降、日本ではさまざまな労働現場に、朝鮮人労働者が受け入れられたが、それが「徴用工問題」や「慰安婦問題」という現代にまで続く、民族間の遺恨となっていることは説明の必要はあるまい。
このように「労力の輸入に頼ってもロクなことにならない」という歴史の教訓を真摯に受け止めれば、「人手不足は外国人労働者の受け入れ拡大で解決」なんて愚かな政策はやめるべきだ、ということを7年前から繰り返し主張させていただいたのである。
「日本人だけで豊かになる」
に伴う“凄まじい痛み”
だが、ご存じのように2018年から外国人労働者は、コロナ禍をのぞいて右肩上がりで増えてきた。2024年10月時点の外国人労働者数は230万2587人。名古屋市の人口とほぼ同じ規模だ。
それだけたくさんの外国人労働者が日本国内にいるということは、それだけたくさんの「低賃金を前提としたビジネスモデルでしか経営ができない零細企業」がいるということだ。
そうなると、産業界からのリクエストに従う政治は「最低賃金の引き上げ」などができない。海外では物価高騰に合わせて最低賃金が引き上げられており、韓国にとっくに追い抜かれて、台湾に抜かれるのも時間の問題だ。
「最低賃金を引き上げると倒産があふれるのでしょうがない」というが、これも100年以上続く低賃金カルチャーが見せる「幻想」で、実際は大正期と同じく低賃金労働者のおかげで、倒産どころか好業績を叩き出している。