「East-i」から約30年の技術の進歩を反映して、時速320キロでの検測を可能とし、営業車両と同様の自動運転導入も視野に入れる。レールの軌道変位検測装置は2次元レーザーを導入して細かく正確なデータ取得を可能とする。また、これまで保守用車から人が目視していた電車線金具の検査もカメラを用いた画像モニタリングで代替するなど、検測の省人化や遠隔化を進める。
ちなみに、JR東日本は2024年12月から、新幹線の線路モニタリング車両「SMART-Green/Red」を用いた「スマートメンテナンス」を行っている。「East-i」との検測内容の違いを聞いたところ、前者は材料の劣化や不良などなど材料状態を測定し、後者は軌道変位(歪み)や列車動揺(揺れ)を主に数値で測定しているそうだ。
ところで、「ドクターイエロー」の異名で知られる東海道・山陽新幹線の「923形」は、JR東海所属車両が今年1月に引退し、JR西日本所属車両も2027年頃に引退する計画で、後継車両は作られない。九州新幹線は開業時から営業車両にセンサーを搭載して検測しており、JR東海、JR西日本も「N700S」で代替する。
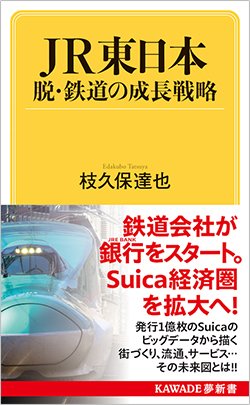 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
JR東日本とそれ以外で判断が分かれたのは、同社特有の新幹線ネットワークが関係する。一本道の東海道・山陽・九州新幹線に対して、JR東日本は5方面の路線を有するため、それぞれの営業車両に搭載するより、全ての路線に入れる総合検測車を用意した方が効率的なのだ。そして、その役割はミニ新幹線の車両でしか果たせない。
こうして役目を終えると思われた「E3系」だが、新たな役割で今秋から再び走り出す。それが山形新幹線を引退した車両1編成(7両)の全座席を撤去し、1000箱単位の段ボールを搭載できる荷物輸送専用車両、いわば「荷物新幹線」だ。
もう11月が目前だが、「今秋」のまま続報がない。山形新幹線では今年6月、新型車両「E8系」計5編成で補助電源装置が故障するトラブルが発生した。原因究明まで「E8系」の運用を見合わせたため、「E3系」が引退を延期して最後の奉公をした経緯があり、改造が遅れているのかもしれない。
荷物新幹線が2029年度までに廃車になる可能性はあり、「East-i」とどちらが最後の「E3系」になるか分からないが、もうしばらくは雄姿を見られそうだ。







