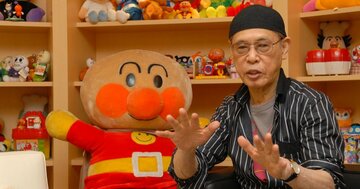大東亜戦争は満洲事変から
始まったとする15年戦争史観
それでは、あの戦争の起点は、1937年7月7日なのだろうか。
いや、もっとさかのぼって考えるべきだという意見も昔から根強い。満洲事変こそ、日中間の武力衝突の発端だとする立場である。
満洲事変は、1931(昭和6)年9月18日、奉天(現・瀋陽)郊外の柳条湖で関東軍が引き起こした鉄道爆破事件に端を発する。関東軍はこの事件を中国側の仕業と主張し、自衛を名目に軍事行動を開始した。その結果、現在の中国東北部に満洲国が建国されるにいたった。
満洲は、日露戦争後に日本が鉄道や附属地などをロシアから獲得した地域であり、当時日本領だった朝鮮半島と隣接し、ソ連との国境にも接する戦略的に重要な拠点だった。加えて、石炭や鉄鉱石の供給源としても価値が高く、日本にとって軍事・経済の両面で不可欠な場所と考えられていた。
そのため、日本軍は満洲国を確保したのちも、中国との国境地帯にあたる華北を自国の影響下におこうとする「華北分離工作」を推し進めた。いわば、第二、第三の満洲国をつくり、満洲国を守ろうとしたわけだ。
これが中国側のナショナリズムを強く刺激し、日中戦争が局地的な軍事衝突にとどまらず、全面戦争へと発展する遠因ともなった。
こうした背景を踏まえて、満洲事変を起点としてあの戦争を捉える歴史観を15年戦争史観という(実質は14年に満たないが、足掛け15年と考える)。
この歴史観は、満洲事変・日中戦争・大東亜戦争という3つのできごとを必然的に結びついた連続した戦争と捉える。その背景には、日本が大陸侵略を一貫して計画的に進めてきたという見立てがある。
そのため、左派的な歴史観とされることが多いが、教科書や一般書を通じて広く浸透している考え方でもある。
上皇の言葉ににじむ
左翼的史観の影
その普及のほどを象徴するのが、平成の天皇(現・上皇)が2015(平成27)年1月、戦後70年の節目に発したつぎの発言だ。