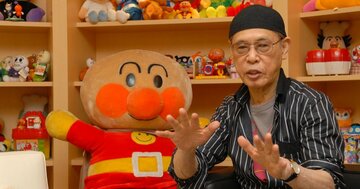写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
戦後80年を迎えた今、“あの戦争”をなんと呼ぶのかということについては専門家の間で未だに議論が分かれている。さまざまな呼称が飛び交う中で、近現代史研究者の筆者が導き出した「答え」とは?※本稿は、辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。
戦争の呼び方には
政府の意図が隠されている
歴史を正しく捉えるには、形式ではなく実態を見極める必要がある。この論理は、現代のわれわれにとって十分理解しうるものだろう。
ロシアは2022(令和4)年2月にウクライナへ侵攻したが、この戦いを一貫して「特別軍事作戦」と称し、公式には戦争であることを認めていない。
この呼称への固執には、ロシア国内の政治的事情が深く関わっており、その背景を理解することは、ロシアという国家の内情を把握するうえで欠かせない。
しかし、それを理由に、われわれがただちに「ロシアの主張を尊重し、あれは戦争ではない」と考える必要はない。実態を踏まえれば、それが戦争であることは明白であり、そう断言することになんの支障もないのである。
同じことは、かつての日本にも当てはまる。日本政府が日中戦争を支那事変と呼んだ背景には、外交的・政治的な意図があった。その意図を理解することは、当時の日本の内情を知るうえで欠かせない。
しかし、呼称にこだわるあまり、実態を見失ってしまっては本末転倒となってしまう。
日中戦争は、双方あわせて数百万人以上もの兵士が動員され、広大な戦域で繰り広げられた大規模な武力衝突だった。それを戦争とみなすことは歴史的事実として妥当であり、むしろ不可避とさえいえる。